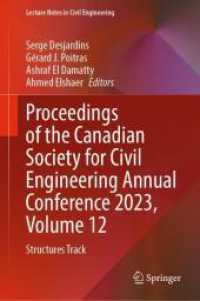出版社内容情報
東アジアの文化の根底をなす書は、「弧島」の舞台でいかなる劇を繰り広げたの
か? 書を筆蝕の美学と捉える視点から、古代から明治初年までの代表的作品に定
着された精神の軌跡を、その表現に即してひとつひとつ丹念に明らかにし、それを
通じて日本書史の全体像を提示した、著者のライフワーク。
≪第56回毎日出版文化賞受賞≫
目次:
序章 書の見かた/ 途中乗車し、途中下車した日本の書史は何を描き出したか/ 書
から見た日本史の時代区分
[第一部 中国時代]
第1章 金印論――日本語の形成:「漢委奴国王印」
第2章 弧島中国時代の宛字遺品:張安「江田船山古墳出土鉄刀銘」
第3章 古風とやさしさと:聖徳太子「法華義疏」
第4章 大陸・半島・倭――入り乱れた書風:「宇治橋断碑」
[第二部 擬似中国時代]
第5章 大陸と連動する書:「金剛場陀羅尼経」
第6章 大陸中央級の写経:「和銅五年長屋王願経」
第7章 繊細さと、構想の大きさ:聖武天皇「雑集」
第8章 意志の化成:光明皇后「楽毅論」
第9章 仮名文字創製への苦悩:「万葉仮名文書」
第10章 敬虔な学徒:最澄「久隔帖」
第11章 少年の書:空海「風信帖」
第12章 中国への異和:空海「益田池碑銘」
第13章 奇怪の書:嵯峨天皇「光定戒牒」
第14章 日本書史上の絶品:橘逸勢「伊都内親王願文」
[第三部 日本時代(Ⅰ)]
第15章 無法の書と女手:醍醐天皇「白楽天詩句」
第16章 書の『古今和歌集』:小野道風「屏風土代」
第17章 繊細・優美な日本語の姿:藤原佐理「詩懐紙」
第18章 日本文字の完成:藤原行成「白楽天詩巻」
第19章 日本語の声づくりの歌:「自家集切」
第20章 詩型をもって現れた和歌:「秋萩帖」
第21章 「女手」の典型:「高野切第一種」
第22章 滋味の書:「高野切第二種」
第23章 まばゆい速度に主律された女手:「高野切第三種」
第24章 仮名文字の文法:「寸松庵色紙」(上)
第25章 仮名の典型:「寸松庵色紙」(中)
第26章 言葉と構成:「寸松庵色紙」(下)
第27章 冊子に書かれた和歌:「継色紙」
第28章 危険な仮名書:「升色紙」
第29章 典型を超える魅惑の地平:「関戸本古今集」
第30章 古典期を脱する速度感:「曼殊院本古今集」
第31章 「訓」の字姿:「粘葉本和漢朗詠集」
第32章 「ゝ」のひねり:「小島切」
第33章 新しい段階の女手:「香紙切」
第34章 姿を現し始めた筆者:「紙撚切」
第35章 『古今和歌集』以後:「針切」
第36章 おおどかな世界:「西本願寺本三十六人集」
第37章 「序・破・急」の美学:「源氏物語絵巻」
第38章 絵は文字になり:藤原伊行「葦手下絵和漢朗詠集」
第39章 文字は絵になり:「葦手歌切」
第40章 文字の意匠:「伊勢物語切」
第41章 『古今和歌集』と『千載和歌集』の間:西行「一品経和歌懐紙」
第42章 女手の写経:「法華経方便品(竹生島経)」
第43章 崩れゆく骨格:「平家納経(安楽行品)」
第44章 登場した「角度」:藤原俊成「昭和切」
第45章 作者の誕生:藤原俊成「日野切」
第46章 筆記の書:藤原定家「近代秀歌」
第47章 律動の失調に隠された謎:藤原定家「小倉色紙」
第48章 「仮名文」と美学――女房奉書論
[第四部 日本時代(Ⅱ)]
第49章 日本語の字姿:後鳥羽上皇「熊野懐紙」
第50章 民衆の登場と「書きつける」書:親鸞「正像末和讃」
第51章 熱狂の書:日蓮「神国王御書」
第52章 直球の連投、交えられる変化魔球:道元「普勧坐禅儀」
第53章 新しい中国書の流入と定着:一山一寧「雪夜作」
第54章 親中国と脱中国の二面の書:虎関師錬「花屋号」
第55章 仮面の表現:雪村友梅「梅花詩」
第56章 和漢折衷の書:宗峰妙超「渓林偈」
第58章 孤絶した中世禅僧の書:一休「虚堂和尚普説語」
第59章 掛軸の原風景:江月宗玩「年々好日々好」
第60章 近世墨蹟の行手を暗示:隠元「三幅対」、即非「双幅」
第61章 意匠の書:本阿弥光悦「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」
第62章 「散文」の思想:近衛信尹「六義屏風」
第63章 流儀書道の良品:松花堂昭乗「三十六歌仙色紙」
[第五部 日本時代(Ⅲ)]
第64章 古典と歴史の発見:近衛家熙「萬代帖」
第65章 江戸期の西行:松尾芭蕉「かしまの記巻」
第66章 書ならざる書:白隠「巌頭和尚語」
第67章 伸縮自在の絡繰細工:寂厳「飲中八仙歌」
第68章 筆蝕の直接性と不立文字:慈雲「常在霊鷲山」
第70章 散文の世界:与謝蕪村「俳仙群会図自画賛」
第71章 漢詩の蕪村:池大雅「徐文長詩四種」
第72章 「懶し」の構造:良寛「七言詩二篇」
第73章 骨格の構築:北島雪山「花竹琴書詩酒詩」
第74章 「唐様」の書の実力:頼山陽「修史偶題」
第75章 近代書道家の嚆矢:市河米庵「清人詩」
第76章 唐様の仮面をつけた御家流:巻菱湖「白楽天賀劉蘇州恩賜金紫」
第77章 書斎の書:貫名海屋「白玉井銘并叙」
終章 新たな段階への扉
目次
第1部 中国時代(金印論‐日本語の形成―「漢委奴国王印」;弧島中国時代の宛字遺品―張安「江田船山古墳出土鉄刀銘」 ほか)
第2部 擬似中国時代(大陸と連動する書―「金剛場陀羅尼経」;大陸中央級の写経―「和銅五年長屋王願経」 ほか)
第3部 日本時代(1)(無法の書と女手―醍醐天皇「白楽天詩句」;書の『古今和歌集』―小野道風「屏風土代」 ほか)
第4部 日本時代(2)(日本語の字姿―後鳥羽上皇「熊野懐紙」;民衆の登場と「書きつける」書―親鸞「正像末和讃」 ほか)
第5部 日本時代(3)(古典と歴史の発見―近衛家煕「万代帖」;江戸期の西行―松尾芭蕉「かしまの記巻」 ほか)
著者等紹介
石川九楊[イシカワキュウヨウ]
1945年福井県に生まれる。1967年京都大学法学部卒業。現在、書家、京都精華大学教授・文字文明研究所所長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。