出版社内容情報
ストーリーテリングがプロダクトデザインに与える強力な違いを学ぶ!
本書では、ストーリーテリングがプロダクトデザインにどのような影響をもたらすかを紹介します。映画やフィクションで試行錯誤された原則をデザインやビジネスの文脈に応用することで、優れた製品体験を生み出す方法を学びます。伝統的なストーリーテリングの原則、ツール、手法が、プロダクトデザインの重要な側面とどのように関連しているかを探り、プロダクトを伝え、売り込み、プレゼンテーションする方法を取得します。
内容説明
1~3章では、ストーリーテリング理論にまつわる背景やコンテキスト、プロダクトデザインとの関連性、そしてデジタル体験の現状とこれから向かう方向性について考慮すべきことを説明します。実践的な内容というより理論的な内容で、本書の土台を形成しています。4~13章では、伝統的なストーリーテリングから何を学び、その教訓をプロダクトデザインにどう生かすかについて明確に考察します。UXデザインに関連する重要な側面を取り上げ、伝統的なストーリーテリングの原則、ツール、手法との類似性を示します。14章では、自分のストーリーを伝え、プレゼンすることの重要性を紹介します。
目次
第1章 なぜストーリーテリングが重要なのか
第2章 優れたストーリーの解剖学
第3章 プロダクトデザインのためのストーリーテリング
第4章 プロダクトデザインの感情的側面
第5章 ドラマツルギーによる経験の定義と構造化
第6章 プロダクトデザインにおけるキャラクター開発の活用
第7章 プロダクトの設定とコンテキストを定義する
第8章 プロダクトデザインのためのストーリーボード
第9章 プロダクト体験の形を視覚化する
第10章 メインプロットとサブプロットをユーザージャーニーとフローに適用する
第11章 プロダクトデザインにおけるテーマとストーリー開発
第12章 CYOA(choose‐your‐own‐adventure、きみならどうする?)ストーリーとモジュールデザイン
第13章 シーン構造をワイヤーフレーム、デザイン、プロトタイプに適用する
第14章 あなたのストーリーの発表と共有
著者等紹介
Dahlstr¨om,Anna[DAHLSTROM,ANNA] [Dahlstr¨om,Anna]
アンナ・ダールストレム。ロンドンを拠点とするスウェーデン出身のUXデザイナー。UXデザインスクール「UX Fika」の創設者。2001年以来、ウェブサイトやアプリからボットやテレビUIまで、様々なブランドやプロジェクトにおいて、クライアントサイド、エージェンシー、スタートアップで活躍。定期的に講演活動も行っており、コペンハーゲンビジネススクールでコンピュータサイエンスとビジネス管理の修士号を取得
中橋直也[ナカハシナオヤ]
UX・サービスデザイナー。日本電気株式会社にてデザインコンサルタントとしてDX戦略コンサルティングに関わり、プロダクト、サービス、システムの設計に従事。特定非営利活動法人人間中心設計推進機構(HCD‐Net)認定人間中心設計専門家、認定スクラムプロダクトオーナー(RPO)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むらさき
Go Extreme
ヒデアキ
小泉岳人
ヒデアキ
-
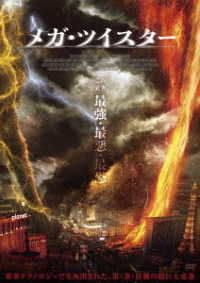
- DVD
- メガ・ツイスター


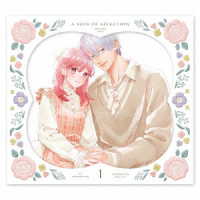

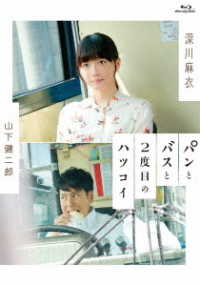
![赤と黒<ノーカット完全版>コンパクトDVD-BOX[期間限定スぺシャルプライス版]](../images/goods/ar/web/vimgdata/4988013/4988013564282.jpg)


