出版社内容情報
冷戦後の一見安定した秩序の中で「資源の配分」としての性格を強めた政治は,テロや武力行使が頻発し激しい対立が顕在化した今日には,通用し得ない。そこで秩序変容の時代のリーダー像が求められる。しかし近代日本においてリーダーはリーダーたりえたのか。彼らの生い立ちから性格まで,そして彼らを取り巻く国際的な事象の拡がりに注目して,指導者達の成功と失敗の要因を炙り出す。
はしがき
第I部 近代国家日本の軌跡――「文明標準」とその解体の中で
総 論………中西 寛
第一章 危機の連鎖と近代軍の建設………小林道彦
――明治六年政変から西南戦争へ
一 士族反乱と外征論
二 徴兵制軍隊をめぐる権力状況
三 危機の切迫と大久保内務卿による兵権掌握――佐賀の乱
四 大久保のリーダーシップの動揺と恢復――台湾出兵の失敗
五 挙国一致への動き――山県陸軍卿の復権
六 西南戦争と琉球処分
七 徴兵制反対論の消滅――板垣退助と自由党土佐派
第二章 明治日本の危機と帝国大学の〈結社の哲学〉………瀧井一博
――初代総長渡邉洪基と帝国大学創設の思想的背景
一 忘れられた初代?東京大学?総長
二 その生涯
三 帝国大学への道
四 帝国大学創設の思想的背景
五 渡邉の見た「夢」――帝国大学体制の虚実
第三章 東アジア「新外交」の開始………中谷直司
――第一次世界大戦後の新四国借款団交渉と「旧制度」の解体
一 大戦後の国際政治と日本
二 新四国借款団をめぐる二つの論点
三 日本外交は旧秩序を守ろうとしたのか
四 首相・原敬の強硬論
五 イギリスの政策――「旧外交」のチャンピオンが目指したもの
六 決着――何が保証されたのか
七 一九二〇年後――新四国借款団交渉がもたらしたもの
第四章 北?吉の戦間期………クリストファー・W・A・スピルマン
――日本的ファシズムへの道
一 大正デモクラシーへの批判
二 日本外交への批判と戦争論
三 アジア主義論
四 ファシズムへの傾倒
五 おわりに
第五章 戦間期における国家建設………等松春夫
――「満洲国」とイラク
一 はじめに
二 戦間期の国際秩序と国家建設
三 イギリスとイラクの建国(一九一九?三二年)
四 日本と満洲国の建国(一九〇五?三二年)
五 分析的な結論
第六章 総力戦・衆民政・アメリカ………森 靖夫
――松井春生の国家総動員体制構想
一 統帥権独立をいかに克服するか
二 松井春生の国家総動員体制構想
三 構想の修正――政党内閣制の崩壊と永田鉄山の死
四 松井春生と日中戦争――国家総動員法制定へ
五 松井春生の国家総動員体制構想とは何だったのか
第七章 高碕達之助と日印鉄鋼提携構想………井上正也
――アジア・シューマン・プランの夢
一 朝鮮戦争と東南アジア開発
二 高碕達之助と鉄鋼業
三 インド鉄鋼開発計画の浮上
四 高炉建設と鉄鉱資源開発
五 日印交渉
六 高碕構想の挫折
七 経済開発とナショナリズム
第II部 リーダーシップを見る視点
総 論………伊藤之雄
一 近代日本のリーダー研究の意義――はじめに
二 五論文(五人)のリーダーシップの概要
三 公共性のある日本独自のビジョンと現実性
四 精神的強さ
五 人間関係と気配り
第一章 木戸孝允と薩長同盟………齊藤紅葉
――慶応元年から慶応三年
一 薩長同盟と木戸孝允の関係――はじめに
二 ペリー来航による国家認識と薩長提携の意識
三 木戸の長州藩主導と、薩長主導の武力討幕
四 明治政府での薩長主導体制と木戸の影響力の喪失
五 薩長同盟と木戸のリーダーシップ――おわりに
第二章 第一次護憲運動と松田正久………西山由理花
――「松田内閣」への期待
一 栄光と忍耐の表れ――はじめに
二 松田正久の政治構想と政治指導の形成
三 護憲運動の盛り上がり
四 原敬に後事を託す
五 第一次護憲運動における公共性の表れ――おわりに
第三章 幣原喜重郎と国際協調………西田敏宏
――北京関税会議・北伐をめぐる外交再考
一 幣原外交に対する「自主外交」批判――はじめに
二 外交指導者としての幣原の個性の形成
三 自主的協調外交としての第一次幣原外交
四 幣原外交はなぜイギリスとの間で摩擦を招くことになったか
五 イギリスとの協調の失敗とその帰結
六 幣原の外交指導の特質とその後――おわりに
第四章 田中義一と山東出兵………小山俊樹
――政治主導の対外派兵とリーダーシップ
一 「おらが宰相」の失敗――はじめに
二 生い立ちと軌跡
三 陸相時代の「転換」から政党総裁へ
四 第一次山東出兵――政治主導の出兵過程
五 第二次・第三次山東出兵――軍事衝突とリーダーシップの崩壊
六 天皇・宮中との対立、張作霖爆殺事件の真相公表をめぐって――おわりに
第五章 平沼騏一郎と政権獲得構想………萩原 淳
――平沼内閣の模索と挫折 一九二四?三四年
一 政権獲得構想に見る平沼のリーダーシップ――はじめに
二 司法官僚としての台頭と政治的性格の形成
三 政治基盤の形成と「田・平沼」内閣構想
四 政権獲得構想の一時的退潮と田中内閣との協調
五 平沼待望論の高まりと平沼内閣運動
六 平沼のリーダーシップの特質とその限界――おわりに
あとがき
索引
伊藤 之雄[イトウ ユキオ]
編集
中西 寛[ナカニシ ヒロシ]
編集
内容説明
冷戦後の一見安定した秩序の中で「資源の配分」としての性格を強めた政治は、テロや武力行使が頻発し激しい対立が顕在化した今日には、通用し得ない。そこで秩序変容の時代のリーダー像が求められる。しかし近代日本においてリーダーはリーダーたりえたのか。彼らの生い立ちから性格まで、そして彼らを取り巻く国際的な事象の拡がりに注目して、指導者達の成功と失敗の要因を炙り出す。
目次
第1部 近代国家日本の軌跡―「文明標準」とその解体の中で(危機の連鎖と近代軍の建設―明治六年政変から西南戦争へ;明治日本の危機と帝国大学の“結社の哲学”―初代総長渡邉洪基と帝国大学創設の思想的背景;東アジア「新外交」の開始―第一次世界大戦後の新四国借款団交渉と「旧制度」の解体 ほか)
第2部 リーダーシップを見る視点(木戸孝允と薩長同盟―慶応元年から慶応三年;第一次護憲運動と松田正久―「松田内閣」への期待;幣原喜重郎と国際協調―北京関税会議・北伐をめぐる外交再考;田中義一と山東出兵―政治主導の対外派兵とリーダーシップ ほか)
著者等紹介
伊藤之雄[イトウユキオ]
京都大学大学院法学研究科教授。1952年生まれ、京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学、博士(文学)
中西寛[ナカニシヒロシ]
京都大学公共政策大学院教授。1962年生まれ、京都大学大学院法学研究科博士課程退学、法学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バルジ
takao
-
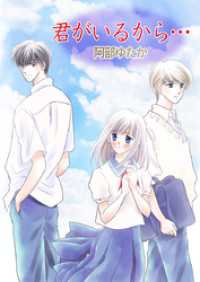
- 電子書籍
- 君がいるから…【タテヨミ】第51話 p…







