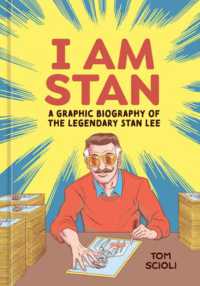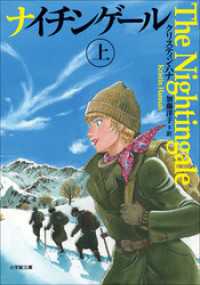内容説明
人々に勇気を伝え続けたのはラジオだった。発災から108時間にわたって情報を伝え続けた。ラジオの存在と役割を改めて問う、ドキュメント&証言の記録。
目次
1 IBCラジオの108時間
2 証言記録「東日本大震災とIBCラジオ」(「被災地にラジオを送ろうキャンペーン」顛末記;あのときのラジオ、これからのラジオ;安否情報発信の現場;ラジオ送信所への燃料補給;炊き出しで報道を後方支援;受話器の向こうの声に寄り添う;被災当日の宮古を取材;伝えたいのに伝える術がない思いに応えたい;いつもラジオが流れていた;情報が安心と勇気を与えてくれた;ラジオは文化財レスキューの命綱)
3 座談会「ラジオが聴こえた夜」
1 ~ 1件/全1件
- 評価
震災を考え続ける本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Roko
36
2011年3月11日に発生した地震によって、これまでに誰も経験をしたことがない大津波が押寄せ、甚大な被害を生みました。電気が止まり、ネットもつながらない状況で、人々に情報を伝えるためにICB岩手放送の方々は、108時間ノンストップでラジオ放送を続けました。電気が止まってしまったのでテレビを見ることはできません。こんな時だからこそラジオ放送だったのです。あの頃よりもラジオを聞いている人は減っています。でも、いざという時にはラジオなのだということを忘れてはいけないのです。災害は忘れた頃にやってくるのですから。2024/11/02
百太
28
そうそう、当日から3日間は、ラジオだけ聞いていました。想像がつかずにいたかな。 第一波60cmを話してしまったアナウンサーの苦悩は、続くのだろうと・・・。 2017/03/22
ikedama99
6
出張先の本屋で見つけました。何となく引かれるものがあって購入。帰りのバスで一気に読みました。これまで震災関係の本は読まずに来ましたが、テーマが「ラジオ」ということで、自分もTVよりもお世話になっているメディアがどう「あの時」に動いたのかを知りたい思いで読みました。読んで、そしてCDを聴き、その当時の方々の必死さと声で人に寄り添うことの大切さを大事にしたアナウンサーやスタッフ、IBCの地元への姿勢などがよくわかりました。「襟を正す」そんな気になった1冊です。2013/02/26
チャーリイ
5
ラジオが、無条件に住民に近いマスメディアと言えるとは思えない。例えば、普段ラジオを聴く人間は必ずしも多くない。ラジオ無しの生活が成立している人にとって、ラジオは近しいものでもなんでもない。 そういう時代の中で、「県民のラジオ」として県民に絶大なる支持を受けていたIBC岩手放送だからこそ、災害時に力を発揮できたのだと思う。2013/08/04
のりーの
4
声を聞けば顔が浮かぶ。懐かしいIBCアナウンサーたち。落ち着いて放送し続けた周りのスタッフたち。地に足の着いた日頃の放送があるからこその放送に対する信頼感。2012/09/17