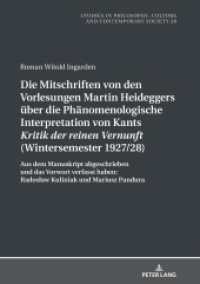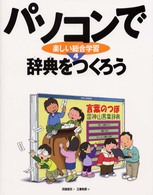内容説明
本書は、ソクラテス・プラトンからフーコー・デリダにまでいたる哲学の歴史を、新たな哲学史観にもとづいて、わかりやすく示している。
目次
第1部 古代ギリシア哲学(ソクラテス以前の自然哲学;アテナイの哲学;ヘレニズム・ローマ帝政期の哲学)
第2部 中世哲学(中世哲学の基本的性格;教父哲学―アウグスティヌス;スコラ哲学―トマス・アクィナス)
第3部 近世哲学(近世哲学の構図;ルネッサンス;大陸合理論;イギリス経験論;ドイツ観念論)
第4部 現代哲学(生の哲学と実存主義;現象学;ヘーゲル左派;分析哲学;ポスト構造主義・ポストモダン)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
5
理性について気になっているお人が哲学史を一望したい向きにはうってつけかと。副題になっている「理性の運命の可能性」はおもしろいとっかかりだと思う。中世哲学の大家ジルソンの哲学史分類を受け継いでいて、善か、存在か、という潮流でもってその哲学史観を編んでいる。文句をいえばニーチェの項目は道徳批判の奥義解説が抜けており、味気ない。褒め称えたいのは巻末にある文章と、理性概念の変遷図。これはすばらしい仕事。理性は普遍性を目指し、おのれの有限性を見出しもする。また宗教上の神と哲学上の神とを分けている序論も一読の価値あり2024/08/16
うえ
4
「スピノザの哲学の全体系は実体概念に基づいている。この唯一の概念から全体系は「幾何学的秩序」によって導かれる。彼によれば、実体とは、「それ自身においてあり」、それ自身によって把握されるもの、すなわち、その概念が他の概念を必要としないで構成されるものである。この考えは…デカルトの実体概念を継承したものであるが、デカルトが三種の実体…を認めたのに対して、スピノザは神のみを実体とした点で異なっている。実体概念を厳密にとれば、精神と物体は有限である限り実体とは言えないからである」2017/07/20