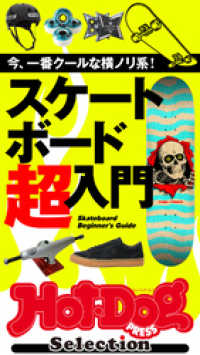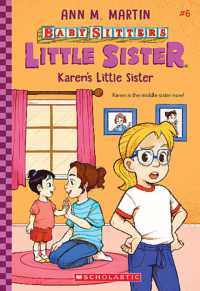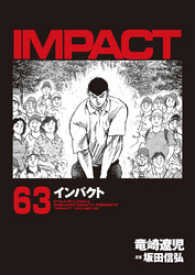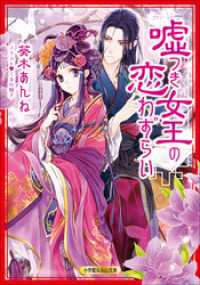内容説明
自然と人為、そして外界と交差する社会の熱量が生み出した環境、公共、文化。大学の諸科学から大阪をガイドする。
目次
第1部 自然と人為―環境とは何か(泉北丘陵の自然―外来植物と人のくらし;大和川の鳥類、哺乳類、両生爬虫類;大阪産(もん)魚介類の調理文化と魚食普及 ほか)
第2部 社会・文化と行政―公共性とは何か(大阪産業労働資料館(エル・ライブラリー)―私立公共図書館という存在
見せる/魅せる仕掛け、博覧会とミュージアム
萩原広道『源氏物語評釈』と近世大坂の出版 ほか)
第3部 イメージと多様性―「大阪」とは何か(大阪方言の地域的多様性とその背景;人形浄瑠璃・文楽と大阪;生駒の神々と近代の大阪 ほか)
著者等紹介
住友陽文[スミトモアキフミ]
大阪公立大学現代システム科学域・教授/歴史学・日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
乱読家 護る会支持!
2
本書で取り上げられているテーマは「泉北丘陵の外来植物」「大和川の鳥類、爬虫類、両生類」「大阪産魚介類の調理文化」「難波の葦」「難波八百八橋の変遷」「熊取町にある京大原子炉」「大阪産業労働資料館」「博物館、美術館の魅せる仕掛け」「大阪の出版物」「大阪の学芸史」「大阪の教育機関」「モノづくりの街、東大阪の進化」「新大阪とディープサウス」「大阪の公営住宅」「大阪の方言の多様性」「文楽と大阪」「生駒の神々と大阪」「坂田三吉」など、、、 2022/08/16
沖縄電鉄社長
1
大学院時代に住んでいた大阪の様々な事柄を、研究者としての視点から語る一冊。大阪の外に暮らす人のみならず、中に暮らしている人が抱きがちな大阪のイメージに再考を促す論考も(とりわけ最後の阪田三吉像)。2022/07/15
三日月和泉
0
典型的な大阪の観光名所を紹介する本ではない。 自然科学・人文社会科学の研究者が同居する大阪公立大学現代科学システム科学域の先生方によって編まれており、舞台は大阪だが対象は様々で、自然・社会・文化の面から大阪について学べる。2024/11/10
もこもこ
0
マニアックに大阪がよく解る1冊でした。2024/09/06