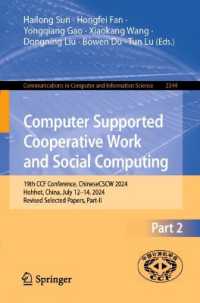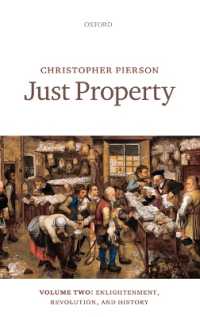内容説明
「民族自決」の帰結と思われた多民族国家ハプスブルク帝国の崩壊と新生国民国家群の成立は、一〇〇年と経たずに限界を露呈した。崩壊と成立という断絶のときに立ち返り、民族で割り切れない人びとの世界に焦点を当てて、国民国家と「民族自決」を問い直す。
目次
「民族自決」という幻影
第1部 アイデンティティのはざまで(ウィーン・ユダヤ人の憂鬱―帝国オーストリアからドイツオーストリアへ;それぞれのユーゴスラヴィア―セルビア義勇軍の理念と実態;聖戦からユーゴスラヴィアへ―大戦とボスニア・ヘルツェゴヴィナのムスリム ほか)
第2部 連続と非連続のはざまで(「名前のないくに」―「小さな帝国」チェコスロヴァキアの辺境支配;帝国の遺産―チェコスロヴァキアの行政改革の事例から;ウィーンにおけるチェコ系学校の「戦後」―「民族の平等」と「少数民族保護」のはざまで ほか)
第3部 記憶と記録のはざまで(文書は誰のものか―複合国家の文書館とハンガリーの歴史家たち;帝国遺産の相続―文書・文化財の移管をめぐる国家間交渉;帝政期の都市の保全活動をめぐって―チェコの労働者住宅の事例から ほか)
著者等紹介
大津留厚[オオツルアツシ]
1952年生。東京大学大学院社会学研究科国際関係論専攻博士課程単位取得退学。大阪教育大学教育学部助教授、神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、神戸大学名誉教授。国際学修士。専門はハプスブルク近代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Fumitaka
3
第一次世界大戦後の旧ハプスブルク帝国を巡る様々な論文集。篠原琢先生のルシン人を巡る論文目当てで読み始めたが、後継国家間での文書の分割(第9章)やオーストリアにおける「戦争責任」を巡る話などはまったく予想外の話題であり、楽しませていただいた。チェコの新しい「県庁・郡庁設置法」(「廃藩置県」だろうか?)が、ハプスブルク時代に対する「断絶」「民主主義の勝利」を強調しつつも、「実際には帝国との連続性も維持されていた」(p. 159)とかは否定しがたく日本っぽい。まあ人間のやることですからね。2023/01/07
ワッキー提督
3
ハプスブルグ帝国崩壊直後の各国に関する論文集。この分野は詳しくないので初見のテーマばかりであったが、チェコスロバキア内における辺境の少数民族に関する論文など、興味深いものが多かった。2021/08/10
まつだ
0
ハンガリーオーストリア二重帝国崩壊による東欧、スラブ民族への影響、当時の政治的背景、条件、継承などの論文集。事情はたくさんあったけれども、ハプスブルク家統治時代には、一つの国家の「雰囲気」はあったんだな、と。崩壊を求めていた大勢の人はいたんだろうか、とか思う。ハプスブルク帝国ありきの上で、目覚めつつあった「民族」という自認にはもっと時間が必要だったのかとか、安易に想像した。第3部が「めんどうくさい仕事」って感じで面白かった。2024/02/11