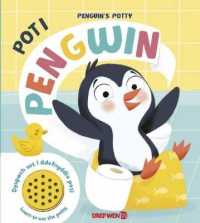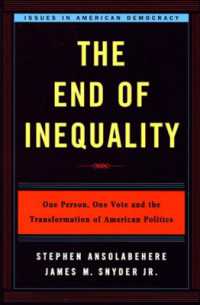出版社内容情報
この150年、日本にも「哲学」はあった。しかし、それらは個々にしか語られてこなかった。その全体像がいま浮かび上がる。
藤田正勝[フジタマサカツ]
著・文・その他
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あっきー
13
✴4 メインの西田、田辺、三木以外は分かりやすくまとめられていて良かった、メインが理解できなかったのは自分の力不足なのだがこれからの課題が明確になった、 大戦前の緊迫した状況下での西田の唯識(唯心論)と京都学派の後輩から突きつけられる現実とのせめぎ合いがスリリングだ、「ある事柄を会得することが、対象の把握であるだけでなく、同時に自己を知ることでもあり、そしてそのことを通して自己自身が内から変化していくような知である』と西谷啓治の紹介にあった、こんな本に出会った時に自分は読書メータで評価✴5つを付けている2019/04/30
さえきかずひこ
12
470ページほどで主に文明開化から昭和時代にかけてのわが国での哲学の受容と発展について要所を押さえつつ簡明にまとめた一冊。明治の哲学受容黎明期に、儒学の学識豊かな西周がフィロソフィーの訳語をどうしようか頭をひねったエピソードは印象的。また、大正時代の哲学が同時代のドイツ哲学(新カント学派〜現象学)の大きな影響を受けていたことも丁寧に触れていて、三木清の著作に改めて触れたくなった。著者が京大で教えていたこともあってか、京都学派の生成と発展について詳しく、戦後の流れも追っているのは無の哲学に関心を深められる。2019/02/03
KJ
2
触れてこなかった日本の哲学史が掴めてありがたい。京大の講義を経て20年以上かかった本というスケール感も素敵。自由思想×儒教というシンプルな図式から仏教やドイツ哲学が入り交じった「絶対」や「国家」に向かう流れは偶然か必然か。現象学をはじめケアの理論も西田哲学の注釈として読めてしまうのかなとか明治以前は儒学(朱子学?)がどう受容され機能していたのか、今もどう生き延びているかなど、色々興味が湧いてくる。個人的に三木清(構想力)、九鬼周造(日本の詩)、若林恵(ペルソナ)あたりの思想家や概念も特に掘りたくなった。2025/12/22
俊介
1
構想から完成まで20年を要したとされるかなりの力作。500ページの大著なので時間かかったけど、時間かけても読むだけの価値、強度はあったと思う。「哲学史」なので時代範囲は西洋哲学を受け入れてからの、明治、大正、昭和だ。その時々の代表的な哲学者たちの思想を、時代背景や、前後の哲学の流れと関連させながら分析、解説していくのだが、とにかく取り上げられる哲学者の数の多いこと。しかもそれぞれきちんとエッセンスを汲み出しており、単なる哲学事典に終わってないと思う。また、なんと言っても著者の解説が分かりやすい。2018/12/27
takao
0
ふむ2025/06/18