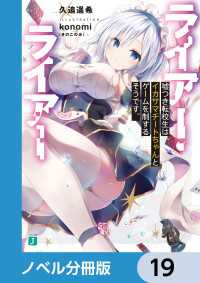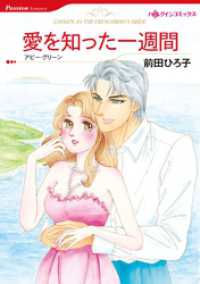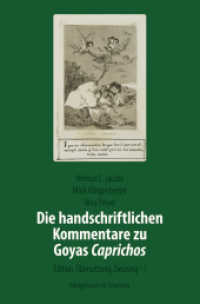内容説明
「琉球・沖縄」の表象と多様性、「琉球処分」や「日本復帰」を結び目とする歴史、そしてそこから私たちは何を学ぶことができるのか―4つの視点から沖縄学の蓄積を検証しつつ、沖縄が直面する現実の課題に多面的に挑む。はじめて学ぶ「沖縄学」テキスト。
目次
1 歴史(三人の「琉球人」―史料を読む;「方言論争」をたどりなおす―戦時下沖縄の文化・開発・主体性 ほか)
2 芸術・思想・文化(琉球舞踊と身体―舞踊技法研究の魅力;沖縄の宝―沖縄音楽における伝統と革新 ほか)
3 言語・文学・表象(沖縄のわらべ歌で学ぶウチナーグチ;山之口獏「会話」を読む―近代沖縄文学の葛藤 ほか)
4 社会・政治(周縁社会の人の移動と女性の役割―奄美・沖永良部島民のアイデンティティと境界性;「集団自決」と沖縄戦―戦場における「国民道徳」と「従属する主体」 ほか)
著者等紹介
勝方=稲福恵子[カツカタイナフクケイコ]
1947年沖縄具志川村(現うるま市)生まれ。早稲田大学文学研究科博士後期課程(現代アメリカ文学専攻)単位満期取得。現在、早稲田大学国際教養学術院教授、早稲田大学琉球・沖縄研究所所長、沖縄県「女性史」編集委員、那覇市「市史」編集委員、「沖縄文化協会賞」運営委員・審査委員など。研究分野は、ジェンダー/エスニシティ論、沖縄学。2002年、沖縄文化協会賞(仲原善忠賞)受賞
前嵩西一馬[マエタケニシカズマ]
1971年沖縄那覇市生まれ。コロンビア大学人類学部博士課程修了。現在、早稲田大学琉球・沖縄研究所客員講師、明治大学および日本大学兼任講師、早稲田大学演劇博物館グローバルCOE「演劇・映像の国際的教育研究拠点」研究員。専門は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。