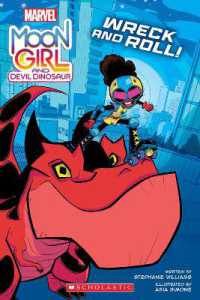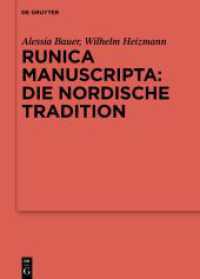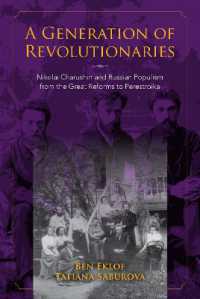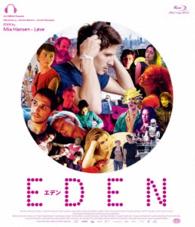- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
「学校に行きたい!」そんな少女たちの夢が、ようやくかなうことになったアフガニスタン。けれども、三十年以上も戦争がつづき、大地も人の心も荒れ果てたこの国で、それはかんたんなことではなくて…。
目次
1 アフガニスタンへの道
2 カブール―戦争の傷あと
3 兄さんは、もういない
4 戦争で失ったもの
5 マリアムの笑顔
6 学ぶことをあきらめない
アフガニスタンという国について
あとがきにかえて―アフガニスタンの昨日と今日、そして明日
著者等紹介
後藤健二[ゴトウケンジ]
ジャーナリスト。1967年宮城県仙台市生まれ。番組制作会社をへて、1996年に映像通信社インデペンデント・プレスを設立。戦争や難民にかかわる問題や苦しみの中で暮らす子どもたちにカメラを向け、世界各地を取材している。NHK『週刊こどもニュース』『クローズアップ現代』『ETV特集』などの番組でその姿を伝えている。『ダイヤモンドより平和がほしい』(汐文社)で、産経児童出版文化賞を受賞。他(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
166
報道ジャーナリスト、後藤健二氏。…カブールの街はまるで廃墟そのものだった。街中は何千年も前の遺跡のよう。タリバンがいなくなったとはいえ、三十年以上も続いた戦争の跡はいたるところにはっきりと残っていた。…学校を知らない母親、行ったことのない女の子。数千人が学びに集まる。ダリ語を勉強して本を沢山読みたい。先生になりたい。子どもの夢はどの国でも同じです。…英国、ソ連、米国、翻弄され続けているアフガニスタン。この二十年間で進んだ子どもへの教育や女性の社会進出の力が、現在の混乱への新たな希望に繋がることを願います。2021/09/05
Kawai Hideki
121
後藤健二さん再び。2001年のタリバン撤退直後に、アフガニスタンの首都カブールに入り、アメリカ軍の誤爆で働き手の長男を失った家族に取材。初めは茫然自失だったが、やがて学校が再開されたことで、取材先の女の子マリアムが希望を持つ。ところが、子供が多すぎて教科書もノートもペンも満足に行き渡らない。マリアムは学校へ行くのを諦めてしまう。それを知った後藤さんが校長に直談判。再入学は認めないという校長に、マリアムは家で密かに勉強を続けていたノートを開くのだった。「テロとの戦い」がもたらした平和とは何かを重く問う。2015/03/21
澤水月
51
後藤健二さんが殺害されてから1年余。アフガンで米軍誤爆により亡くなった青年に「死ぬ瞬間何を思ったのだろう? 家族? 仕事? 戦争への恨みや疑問?」と繰り返し考えている、そのご本人が…。00取材、09刊行。タリバンごいなくなり戻った難民150万人を神戸の人丸ごと分と例えるなど子供にわかりやすい。30年戦争していたため教育を受けた親がおらず、言葉の綾で学校側から来るなと言われたと勘違いする少女、後藤さんが取りなさなければそのまま無教育になるところだった…今どうしてるだろう。やはり惜しい方を亡くしたと思う。2016/03/05
ころりんぱ
51
女性の権利がことごとく軽視される宗教、慣習、生まれる国によって大きな差があるのは仕方ないのかもしれない…だけど、紛争が治まり、学校に通う権利が与えられても、食べること、生きることに精一杯の状況では、通えない。外国に避難していた人たちの生活が復興、発展していく一方で、貧しさから教育を受けられない子どもたちも多くいるという事実がある。格差は不満を呼び、また新たな反政府勢力を発達させるという悪循環。やはりお金以外で子どもたちを救えるのは教育なんだなと思った。こうやって本が読めるのも、教育を受けたからなんだ。2015/03/07
Y2K☮
49
再読。やはり誤爆で家と長男を奪われた一家の話が切ない。彼らからしたらタリバンも米軍も自分達を不当に苦しめたという点では同じ。武力の限界。イラク戦争でフセイン政権が倒れたらISが台頭して却って状況が悪化した様に。これを打破する上で、大手メディアが無視する現地の小さな声を紹介してくれる著者は絶対必要だった。某元知事じゃないけど威勢のいい台詞を好むマッチョ気取りほど、いざ渦中に置かれると腰抜け。真に勇敢な人は黙って勉強し、優しさと謙虚さを失わず、常に当事者として意見を発信し、結果を恐れずに行動する。見習います。2016/10/06