目次
Q1 家計の支出のうち、税金はいくら
Q2 税金と政治
Q3 もうひとつの予算―特別会計とは
Q4 政治と企業のつながり
Q5 命と暮らしを守るために
Q6 住民の暮らしを支える
Q7 子どもの教育のために
Q8 働く人たちを守るために
Q9 平和を築けば、いらない費用
Q10 国債は未来のつけ
著者等紹介
大野一夫[オオノカズオ]
1947年東京都に生まれる。千葉県公立中学校教員・歴史教育者協議会事務局長を経て、東洋大学・武蔵大学講師(非常勤)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のん@絵本童話専門
0
税の歴史や目的、内容が説明されていた1巻2巻。この3巻ではより私たちの暮らし側から捉えた税。より派生した話で税の使われ方について。家計から出ていく税額、政治で使われる税、特別会計、社会保障、国防費、国債、オンブズマン制度など2024/06/04
tatsuya izumihara
0
再読2回目。2000年代当初、派遣の規制緩和により非正規労働者が増え始め、2004年製造業への派遣を認めたためさらに非正規労働者が増えた。企業にとっては都合がいいだろうが格差が広がっている。この法案を作った竹中平蔵氏は派遣会社パソナの役員となっている。製造業は扱ってないというが利益相反ではないのだろうか。現在は非正規労働者の待遇を改善する為に規制をかけているが、そもそも規制を緩め非正規労働者を増やすことに問題があったのではないだろうか。2021/02/28
tatsuya izumihara
0
改めて税金の種類を確認できた。普段あいまいに覚えてることが明確になった。改めて自分の給与明細を見て意外と住民税たかいなあと思った。平成の大合併で市町村は1742となった。2004年の製造業の派遣を認めたことによって派遣労働者増える。2012年から労働期間30日以内の日雇い派遣禁止など改正に動き出した。防衛費は1960~80年まで急激に増えてる。そのあと97年まで増え続け5兆円までふえてきた。PKOは国連の平和維持活動。NGOは民間の国際協力支援組織。個人向け国債は2000年代になってから。2021/02/22
-
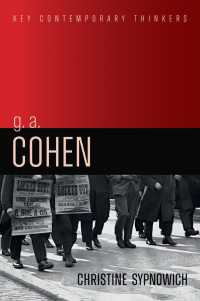
- 洋書電子書籍
- G.A.コーエン:自由・正義・平等(現…





