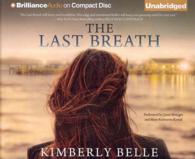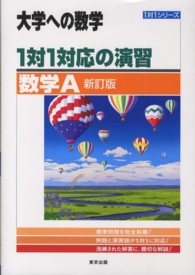内容説明
続発する学級の荒れやいじめ、未成年の凶悪な事件。「私なんて大したことはない」「どう生きたって変わらない」と、捨てばちになった子どもは、刹那的な快楽に身をゆだね、向上心をもてず、社会に敵意を感じ始める。子どもたちの自己肯定感を養うことが急務である。自分を、自分の人生を大切に生きていきたい!カウンセリングで子どもの心を育てる考え方とテクニック。
目次
第1章 自分を好きになれない子どもたち(自分を好きになれない子どもたち;自己否定している子の見分け方 ほか)
第2章 「自分を好き」ってどんなこと?(むなしさの時代に生きる子どもたち;“松田聖子世代”の親とその子どもたち ほか)
第3章 “自分を好きになる子”の育て方(人間関係能力を培う場と時間をつくる;エンカウンターでふれあいの学級風土づくり ほか)
第4章 教師が自分を好きになるために(教師のこころの癒し方;子どもとの関係改革 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
フィリッポ・インザーギ
0
やっぱり、”つながり”が大切。学級の中にいかにその絆、”つながり”を創るか。これが一番大切。
パンパンパン子ちゃん
0
教採二次対策のため読んだ。問題行動を起こす子どもは総じて自己肯定感が低いということで、教師として、親としてどう子どもと関わっていくべきか学んだ。自分を大切に、自分の人生を大切に生きていきたいと思う自己肯定感が生きる力なのではないかという言葉には共感した。知、徳、体のトライアングルがあるが、その基盤として自己肯定感が必要なのではないか。自己肯定感がそれらを伸ばしてくれると感じた。個人的には褒めるということを大切にしていたが、一緒に喜ぶ教師という考え方も今までの自分にない考えであったので新鮮な刺激を受けた。2016/06/29