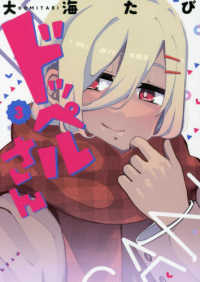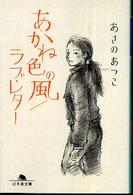- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
出版社内容情報
この絵師、ただ者にあらず――。
幕末土佐で活躍した「絵金」。独特の様式で描く極彩色の「芝居絵屏風」は現代でも高知の夏祭りの花形で、広く親しまれる。代表的な芝居絵屏風、絵馬提灯、絵馬、風俗画、白描画、絵本など多彩な作品を通して絵金の画才を堪能できる画集。
内容説明
恐ろしいほど美しい幕末土佐の天才絵師絵金。
目次
絵金の画業と絵金文化
第1章 絵金が学んだもの
第2章 語り物の表現1 芝居絵屏風
第3章 語り物の表現2 絵馬提灯
第4章 語り物の表現3 絵巻・横幟・白描
第5章 絵金の人柄が伝わる作品
第6章 絵金さんたちの土佐芝居絵屏風
著者等紹介
鍵岡正謹[カギオカマサノリ]
1943年、奈良県生まれ。慶応義塾大学卒業。セゾン美術館(西武美術館)企画学芸部長を経て、高知県立美術館初代館長、岡山県立美術館館長。現在、岡山県立美術館顧問、絵金蔵顧問、高知県立文化財専門委員など
中谷有里[ナカタニユリ]
高知県立美術館主任学芸員
横田恵[ヨコタメグミ]
創造広場「アクトランド」学芸員。2005年より絵金蔵初代蔵長及び学芸員、2017年より現職。南国市文化財保護審議委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
53
あべのハルカスの美術館で開催された「絵金展」にはとうとう、行けず。絵金の絵は画集で楽しむというこじんまりとした鑑賞になりました。絵の元ネタになっている歌舞伎や舞台の筋書きが入り組んでいる上にドロドロしているのに絶句。割腹後のまろび出る腸などを美化することなく、余すことなく、描いた上、背景や家具、人物の配置にも意味を付与しているという高尚な遊び心。血祭りな絵以外は子供のふくふくとした笑顔が何ともチャーミングなのでギャップが凄まじい。そして「卒論の資料に絵金も使えたのかな・・・」と今更ながらに思いました。2023/07/18
m
4
大阪で開催されていた展覧会にあわせて出された本か。絵はどんな話のどの場面か説明がないとわからないのでやや難しいが迫力満点。東京にも巡回してくれれば観に行ったが、本場絵金祭りで蝋燭の灯りの下観るのが一番良いのだろう。2023/08/09
遠い日
4
「絵金」すなわち絵師金蔵については全く存ぜずでしたが、こんなにリアルでかつどこかユーモアさえ秘めたパワフルなアートに惹かれました。土佐の特有の芸術文化だそうで、なんとなく土佐の気風に満ち満ちているという印象です。強調されたグロが却って鑑賞者を煽るというか、よし根性入れて観たろうやないか⁉︎という気にさせられるから不思議。2023/08/04
三井寿里
0
何年も前に、「美の巨人たち」で初めて見て以来、ずっと心惹かれていた「絵金」。なかなか高知まで見に行くことが出来ずにいましたが、この本で彼の来歴から作風、弟子の世代まで知ることが出来て、やはり実物を見たいという気持ちが高まりました。今年の絵金祭は残念ながら終わってしまいましたが、来年こそは足を運びたいと思っています。2023/08/21
-
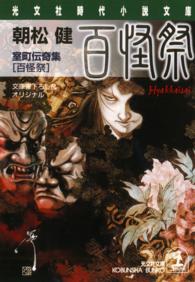
- 電子書籍
- 百怪祭~室町伝奇集~