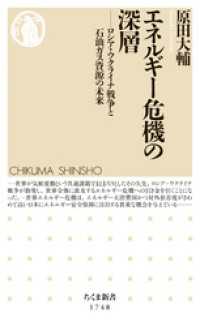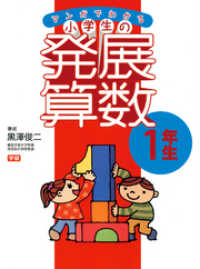- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
目次
序章 一六五八(万治元年)―光琳京都に生まれる
第1章 一六九二(元禄五年)―光琳画家となる
第2章 一七〇四(宝永元年)―光琳江戸へ行く
第3章 一七〇九(宝永六年)‐一七一六(享保元年)―光琳再び京都へ
終章 光琳を継ぐものたち
著者等紹介
仲町啓子[ナカマチケイコ]
1951年、大分県大分市生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。群馬県立女子大学文学部美学美術史学科助手を経て、1985年から実践女子大学に奉職し、同大学教授。専門分野は日本美術史、とくに琳派、浮世絵などの江戸時代の絵画・工芸(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
91
前回の2008年出版から13年経過し、著者は2016年秋田県立近代美術館長(2020年度より特任館長)となり、2020年「光琳論」を出版した。この改訂版では最新の知見をコラムとしてふんだんに盛り込んであり、「徳川家と風神雷神」では光琳の絵画が江戸の武家に渡ることにより宗達とは違う生真面目な表情にしたとある。宗達から50年後に生きた光琳は時代が厳しくなったことで武家に取り入らなければならなかった事情もあった。明治以降に装飾的という西欧の価値観が導入されて、デザインとしても優れていると見られたのかもしれない。2021/09/10
Misae
5
雁金屋草紙を読んで、尾形光琳に興味を持ったのでこちらを手に取ってみた。光琳の生涯を追いつつ、その時期の作品を収録してある。小説を読んだ後なのでそれと照らし合わせて読めてまた楽しかった。たくさんの作品があるが、結構「個人所蔵」というものも多く、こんなすごい物を個人で・・って感心してしまった。まだ世に出てなくて、個人で持ってるものもあるのかも この本で紹介されてた手紙とか遺書とかも雁金屋草紙に出てきていたので、これを踏まえて再度小説読むとまたそれも面白うだろうなと思いました。2024/09/24
takakomama
4
2008年刊を増補改訂。私は、琳派といえば、まっさきに尾形光琳が思い浮かびます。燕子花図屏風や弟の乾山との合作、風神雷神などの他、和菓子の光琳菊もはずせません。ほんの少しですが、修復費を寄付した東京国立博物館の小袖も光琳作なので、思い入れがあります。2022/12/24
菊地
3
西洋画から浮世絵に手を広げている最中で、もう一歩興味を広げようと日本の画家として名前を知っている画家である尾形光琳の入門書として手に取ってみた。 やはり水墨画や大和絵などの基本的な素養が足りていないので、技巧や魅力についてはすんなりと入ってこないところが多かった。不勉強。一方で尾形光琳が再評価されたのは後世になってからだった、みたいな話は興味深く読めました。 改めて「要勉強」ということを再確認できたことを収穫だと思うしかないですね。ゆくゆくはこういった作品群を楽しめるようになりたい。2024/02/10
kaz
3
このシリーズの他のものと同様、尾形光琳の作品の変遷とその生涯を追うことができる。その才能の豊かさは、これまで自分が知っているレベルをはるかに超えていた。図書館の内容紹介は『琳派を代表する尾形光琳の生涯をたどりながら作品100点超をオールカラーで紹介。その魅力と本質に迫る。最新の研究成果を踏まえ、「紅白梅図屛風」に描かれたテーマや「燕子花図屛風」のテクニックを解説した改訂版』。 2022/01/11