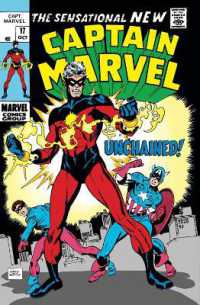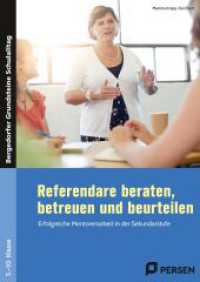- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 絵画・作品集(西洋)
目次
第1章 誕生、画家としてスタート―1881‐1899/0歳‐18歳
第2章 青の時代―1990‐1903/19歳‐22歳
第3章 バラ色の時代―1904‐1906/23歳‐25歳
第4章 キュビスムの時代―1907‐1916/26歳‐35歳
第5章 新古典主義の時代―1917‐1924/36歳‐43歳
第6章 シュルレアリスム、ゲルニカの時代―1925‐1945/44歳‐64歳
第7章 成熟する晩年―1946‐1973/65歳‐91歳
最晩年のピカソ―老いと死への挑戦
著者等紹介
大高保二郎[オオタカヤスジロウ]
香川県生まれ。マドリード・コンプルテンセ大学哲・文学部、早稲田大学文学部(共に博士課程満期退学)。専門はスペイン美術史、バロック美術。跡見学園女子大学、上智大学、早稲田大学を経て、早稲田大学名誉教授
松田健児[マツダケンジ]
熊本市生まれ。上智大学外国語学部イスパニア語学科卒業、学習院大学大学院博士後期課程退学、マドリード・コンプルテンセ大学博士課程単位取得退学。慶應義塾大学商学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
41
26年前にパリのピカソ美術館で鑑賞した《海辺を駆ける2人の女》も紹介されていました。超多才な芸術家の作品群と生き方を多面的に触れることができました。2023/04/23
Y2K☮
33
ピカソ最大の転機はキュビスムだった気がする。極貧に耐えてようやく収めたささやかな成功に甘んじず、スタイルを大きく変えて飛躍した。見据えているものが違う。以後は一時的に「新古典主義」へ戻っても別次元。「ゲルニカ」は私生活の諸々で絵を描けなかった「人生最悪の時」を経て生まれた傑作。「納骨堂」や「朝鮮の虐殺」もそうだが、政治的傾向がどうこうではない戦争全般に対する強い情念に打たれる。あと岡本太郎「青春ピカソ」で気になっていた陶芸を初めて見た。小学校の図工を思い出す。粘土をこねて器を作り、自由に絵付けしてみたい。2022/03/30
らん
21
14歳で描いたデビュー作《初聖体拝領》に魅了され、天才だなぁと衝撃を受けました。妹の死が生涯のライトモティーフとなり、親友の自殺がきっかけで青一色で塗り上げる青の時代へ。青の時代の総決算《人生》はピカソが自らタイトルをつけた数少ない作品だそう。作品への解説だけでなくそこに添えられたピカソの言葉が作品の雰囲気に合っていて良かったです。《居酒屋》がなんだかかわいらしくて好き。ドラ・マールをモデルとした《泣く女》様々なバリエーションがあるけれどどれも印象深い。悲しげな表情から溢れる涙から苦悩、苦痛が伝わります。2023/05/23
スリカータ
17
ピカソ14歳の作品に驚愕。既に完成されている早熟の天才が91年生きると…作風は変わるのは当然。年代毎に追って行くと20代後半に何があった?という変貌。家系図がとても興味深かった。女性関係も派手だが、人生の様々なシーンで女神を得て、生命力や創作意欲を駆り立てられたのだろうと想像。2020/09/10
koke
10
ピカソに対してはどうしても前衛芸術家というイメージを持ってしまう。造形性については今見ても斬新だと感じるが、生と死と異性愛といったテーマ性の部分は古臭くて共感しづらい(《ゲルニカ》の戦争というテーマもその延長にある)。そこが前衛というイメージと食い違って違和感があった。たぶん、キュビスム期の印象が強いせいで先入観を持っていたのだろう。本書のおかげで、キュビスムなどピカソのほんの一部だと思い直せた。2022/10/23
-
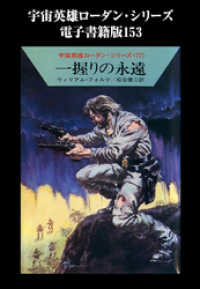
- 電子書籍
- 宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版…