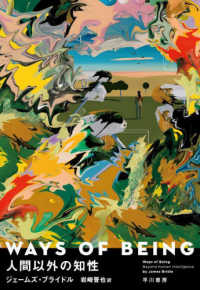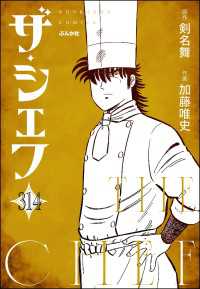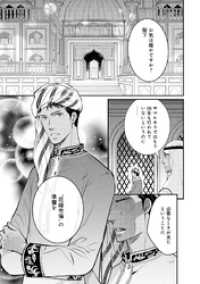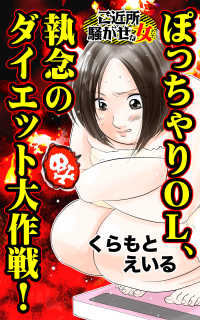内容説明
正倉院の魅力を凝縮!最もコンパクトにまとめられた、「正倉院ガイド」の決定版!約9000件に及ぶ多彩な宝物の中から、名品中の名品とされる105件を厳選し、その見どころをチャートや図版を駆使してわかりやすく解説。正倉院の成り立ちや歴史についても、かかわった人々、特質といった多角的な視点でひもといている。
目次
第1章 名品の魅力を知る(鏡1 螺鈿の鏡―平螺鈿背八角鏡;鏡2 金銀平脱と七宝の鏡―漆背金銀平脱八角鏡と黄金瑠璃鈿背十二稜鏡;鏡3 八卦背の鏡―金銀山水八卦背八角鏡 ほか)
第2章 正倉院の歴史を知る(歴史と伝統1 聖武天皇と平城京;歴史と伝統2 東大寺大仏開眼会;歴史と伝統3 光明皇后の果たした役割 ほか)
第3章 宝物の見方を知る(宝物の特質1 数と種類の豊富さ;宝物の特質2‐1 国際性―西域・中国;宝物の特質2‐2 国際性―朝鮮 ほか)
著者等紹介
米田雄介[ヨネダユウスケ]
1936年、兵庫県生まれ。元宮内庁正倉院事務所長、県立広島女子大学名誉教授、神戸女子大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
井月 奎(いづき けい)
49
正倉院、良いですよねえ。何が良いっていろいろ良いじゃないですか。千三百年近く昔の宝物が色彩豊かに残っている良さ、聖武天皇の、光明皇后の藤原仲麻呂の直筆が見られる良さ、時と場所をシルクロードを経て、今、奈良にあるアフガニスタン算出のラピスラズリの深い青の良さ。ま、私にとって正倉院、何が良いって、一番いいのは九千点を超えるという宝物の数ですね。どんな宝物が眠っているのだろう? こんな琵琶かな?あんな香炉かな?それだったらこういった鏡だってあるんじゃないかな?なんて想像する楽しみをくれるのが嬉しくて好きです。 2020/07/24
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
49
先月、令和初となる奈良の正倉院展に行ってきた。前々から見たかった自然の山岳風景を現している「仮山」が見られて大満足。今回展示されていない他の宝物について、詳しく知りたくなり読んだ1冊。鏡や屏風などの調度品やガラスや漆器、陶器などの飲食器、楽器、文房具など用途別に宝物を分けて、そのカラー写真とともに紹介。後半では、聖武天皇や平城京、宝庫や宝物を作り上げた人など正倉院をとりまく歴史を解説。さらに、豊かな国際色、すばらしい保存、由緒など宝物の特質も解説。正倉院の宝物の素晴らしさを再確認。2019/12/10
びっぐすとん
22
御即位記念「正倉院の世界展」in東京国立博物館で購入。展示会の図録とどちらにしようか迷ったが、正倉院美術館の本を持っているので、宝物だけでなく周辺の説明が載ってるこちらにした。今日見た夾纈(きょうけち)や巻胎(けんたい)の説明があって正解だった。お目当ての五弦琵琶、とても1200年前の物とは思えない、古びたところがないのが驚愕だった。本を見ていると今回展示のなかった品も見てみたくなる。今でも眩い品々で復元も並大抵の苦労ではないようだが、当時はどれだけ貴重な物だったことだろう。タイムスリップして見てみたい。2019/10/24
こぽぞう☆
20
トーハクの正倉院展で購入。図録は今回東京に来た宝物だけだし、高いし、重いし。正倉院が今もあることに感謝!多くの先人たちが守ってきたのだなと。奈良(とその近辺)の方は毎年、規模はそれなりなんだろうけど、正倉院宝物見れて羨ましい。2019/11/24
クラムボン
17
正倉院の宝物は、緻密な細工が施された工芸品。著者の米田さんの一押しは螺鈿装飾の五弦琵琶、とても華やかな楽器です。私の好みは東大寺大仏の開眼会の舞踏で使われた伎楽面。唐やインド、ペルシャなどを彷彿する国際色が豊かな仮面です。まさに修二会の韃靼の踊りです。また米田さん曰く《宝物中でも五指に入る〜金銀文様の琴》は、嵯峨天皇が借用した《銀平木琴》の代わりに返したもの。天皇はこの楽器を手放したくなかったようだ。正倉院の宝物は日本独自の美意識が生まれる前の、華やかだが、やや猥雑で混沌とした美しさがあります。2021/03/27