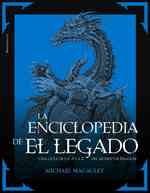内容説明
鑑賞のポイントがわかる!様式・技法・名称など基本の知識をズバリ解説。日本美術の大きな見取り図が頭に入ります。図解でわかる美と技のひみつ。
目次
Prologue はじめての疑問
1 伝統のやきものを知ろう
2 やきもの作りを知ろう
3 やきものの形を知ろう
4 資料編
著者等紹介
伊藤嘉章[イトウヨシアキ]
1957年、岐阜県に生まれる。名古屋大学大学院文学研究科考古学修士課程修了。中・近世の陶磁史を研究。岐阜市歴史博物館を経て、東京国立博物館、次いで九州国立博物館に勤務。2011年に東京国立博物館に戻り、現在、学芸研究部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
20
前半はカラー写真豊富。 後半も白黒ではあるが、 図表、史料、年表いろいろ。 目で食べる和食(4頁)。 磁器は陶器より焼成温度が高い(9頁)。 織部焼は見た事がある(50頁)。 江戸時代の瀬戸焼の製造手順は スケッチでおもしろい(104頁~)。 2014/08/08
昼と夜
11
伊万里いいよ、伊万里。有田焼素敵だよ、佐賀行きたい。只今空前の有田焼ブームが到来中。2014/10/16
海のぱんつ
3
旅にいった松山の大街道あたりで見つけた小さな窯元の作品にみとれてしまってついにやきものの世界をノックしています。時間がないので毎日少しずつじっくり眺めていました。いいなと思ったあのやきものの出自や技法を言葉にしたくて。まだ勉強は始まったばかり。2016/02/22
くろねこ
3
これはコンパクトでカラーで知識満載。図書館で借りたけど、購入候補です。小さいので、博物館に行くときに良さそう!2014/05/28
OjohmbonX
2
日本の陶磁器について、産地別ではなく経時的にコンパクトに整理された本。プロローグの中で、焼き物の産地を問うことは、一義的には①焼かれた場所、同時に②特徴や技法の両者が含まれる(産地ごとに歴史に基づく作風の違いが存在する)が、現在では交通形態が発達して産地と特徴のリンクが必ずしも一致しないが、それでも産地で一定の作風が継承されているので、やはりもともとの産地の特徴を知ることには意味がある、というようなことが書かれていた。一定の枠組みがないと「○○焼」と名乗る意味そのものがなくなってくるのかも、と思った。2023/08/15
-
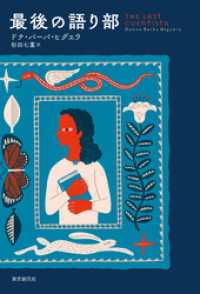
- 電子書籍
- 最後の語り部