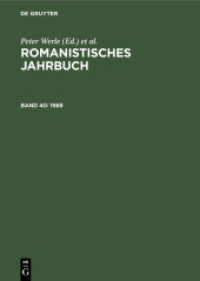内容説明
学生、学芸員、編集者、記者、美術ブロガーなど美術に関する文章を書きたいすべての人へ「美術を言葉で表現する」ためのテクニックが満載。レポートや論文、作品解説、展覧会レビュー等さまざまなタイプの文章を書くことを前提として、「作品の見方」から具体的な文章技術にいたるまで、懇切丁寧に解説。
目次
第1章 美術を書く
第2章 分析
第3章 比較について書く
第4章 展覧会評を書く
第5章 読ませる論文を書くには
第6章 文体
第7章 さまざまな批評方法
第8章 美術史研究
第9章 研究論文を書く
第10章 原稿の書式
第11章 論述式試験
著者等紹介
バーネット,シルヴァン[バーネット,シルヴァン] [Barnet,Sylvan]
1926年生まれ。ボストン近郊、タフツ大学名誉教授。英米文学の中でもシェークスピア研究家として著名で、多数の著作が刊行されている。美術史学、とくに日本美術への造詣が深く、また東洋美術、とりわけ書道美術のコレクターでもある
竹内順一[タケウチジュンイチ]
1941年生まれ。五島美術館学芸部長、東京藝術大学大学美術館館長、茨城県陶芸美術館館長、松本市美術館館長を歴任し、現在は永青文庫館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろ
6
もっと早く欲しかった!色んな論文の書き方やレポートにの書き方本は読んできたけど、やっぱり美術について書くなら美術での書き方を読むにのが一番分かりやすい!何より西洋美術を扱う際に英語が全然分かんない私でも、よく使う単語がトピックスとして挙げられているのが有難い。2014/05/01
gu
5
美術関係の論文執筆に限らず、何か作品について書くこと全般の基本を学ぶ本。特に、言葉ではないものを言葉で語るにはどうすればいいかを知りたい時に。論文も批評も感想も個人的な感動が出発点であり、それを伝えるために論理や技術が必要になる。2024/11/03
OKKO (o▽n)v 終活中
4
読み終わり間近で止まったまましばらくうっちゃっていたが、とりあえず読了宣言 ◆アメリカで芸術学を学ぶ学生はこんなふうにトレーニングしてますよ、という。本書を読むことで、どういう角度から攻めていくべきか勉強になります。が、本書ばっか読んでてもディスクールが上達するわけでないのは当然で、本書を書いたバーネット先生にご指導いただきたいなぁ……と身の程知らずなことを思うのでありました ◆一度通読したらあとは折に触れ必要な箇所を再読すべし。いわゆる教科書的な使い方をしつつ、己の論文を「太い」ものにしてゆきたく2016/03/13
Shogo Iida
3
まずは一番後ろ、367、8頁に目を通してほしい。あなたが美術に関する文章を書く際に突き当たる問題が「チェックリスト」、「よくある質問」としてインデックスになっているからだ。自分に該当する部分を読み続けるうちに、この本が美術のみならず、様々な対象を論述するための良質の手引書であると気付くはずだ。そう、この本はどこから読んでもいい。直面する課題やこれからぶつかるだろう疑問は、決して本文の順番通りに来るとは限らない。いや逆に、そうやって行きつ戻りつするやり方こそ、文章を推敲するという道行に近い形なのだから。2015/04/24
Takao Terui
3
これは本当に良い本。 著者はもとより、翻訳し、持ち込んでくれた訳者にも感謝する。 感性やレトリックが鼻につく、読み応えがない作文が多い美術鑑賞の世界に、笑ってしまうくらい実用的、実務的なマニュアルを持ち込んでくれたのが、非常にありがたい。 教科書・マニュアルを作らせたら、合衆国の右に出るものはいない、と改めて確信させられた。2014/04/06