- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 絵画・作品集(西洋)
目次
1 アルプスの麓に生まれて―1879→1897(クレー少年の夏;アルプスの自然のなかで)
2 修業時代‐クレーのキッチン―1898→1910(画学生クレーの昼と夜;シュヴァービングの静かな日々)
3 色彩との邂逅‐画家の誕生―1911→1919(『カンディード』或いは楽天主義説;「青騎士」の一員に ほか)
4 バウハウス時代 クレーの黄金期―1920→1933(バウハウスの教授として;カンディンスキーとともに ほか)
5 線を引かぬ日はなし―1934→1940(時空を旅するクレー―画家の過去・現在・未来;力の限り描く― ほか)
著者等紹介
新藤真知[シンドウマコト]
日本パウル・クレー協会代表。1950年東京・葛飾区生まれ。都立墨田川高校を卒業後、劇団四季演劇研究所に学ぶ。画廊勤務を経て1974年独立、フリーランサーとして美術展企画制作に取り組み今日に至る。日本初のエッシャー展、シーレ展、クリムト展などを手掛け、1978年からクレー家と親交を結ぶ。1997年に日本パウル・クレー協会を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
324
これまでクレーといえば、青のイメージを持ち続けていた。何に触発されてのことだったのだろう。本書は、薄く簡便な入門書のようでありながら、クレーを再認識するには十分な情報量を有している。5歳の時に描かれた「幼子キリストと列車のあるモミの木」から最晩年の天使の素描まで、クレーの軌跡をたどることができる。こうして通覧すると、クレーはいつもクレーだ。変り映えしないというのではない。そこにはちゃんと変遷の跡もある。しかし、それにもかかわらずクレーは常にクレーなのである。しいて1点を選ぶとすれば「パルナッソスへ」か。2017/11/16
ふみあき
60
今日、地元の美術館で開催中の「パウル・クレー展 創造をめぐる星座」を観に行ってきた。なかなか盛況だったけど、最近の展覧会は「写真撮影OK」ってのが多いみたいで、みんなパシャパシャやってた(私も含めて)。ヴォルテールの『カンディード』の挿絵も展示されていて、久々に同書を読み返したくなった。で、本当は私、前衛芸術は得意じゃなくて、クレーもシュルレアリスムの先駆けともいわれる画家だけど、「色彩画家」である彼の作品は、目も綾な色遣いがとても楽しく、私のようなド素人でも惹き付けられるものがある。2024/11/16
風に吹かれて
25
パウル・クレー(1879-1940)はスイスの首都ベルン郊外のミュンヘンブーフゼーに生まれる。美しい自然にめぐまれた地域。アルプスや湖畔の色彩の中で育った。絶えず画材を工夫しエッチングなどの技法の研究も怠らない。色や形の組みあわせも納得いくまで探究する。ヴァイオリン演奏も楽団に所属していたことがあるほど。 パウロの画に音楽、というよりリズムを感じることがあるが、スイス生まれということを考えると、育った地の景色に想いが行く。 →2022/07/08
sayzk
16
今年、「ルートヴィヒ美術館展」でクレーの作品を見ることがあった。びじゅチューンでもネタになってる。なんとなく名前を知ってたところ、「他人の顔(安部公房)」を読んだらたまたまクレーの絵がでてきた。で。その後「ピカソとその時代とベルリン国立ベルクグリューン美術館展」でまたクレーに出会う。家の近所の小さな図書館の分室で、美術の本なんて数冊しかないのにこの本があった。みんなたまたま。抽象画を解する審美眼があるとは思っておりませんが、色がきれいだと思った。2023/05/02
koke
12
たとえば「天使」連作など、どうしてこんな自由で心地よい線が書けるのかさっぱり分からない。あと本人の写真写りが滅茶苦茶よくて、いつもチャーミングでユーモアを漂わせている。2022/09/10
-
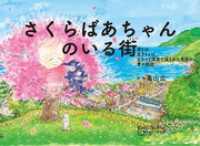
- 電子書籍
- さくらばあちゃんのいる街 ポット出版プ…




