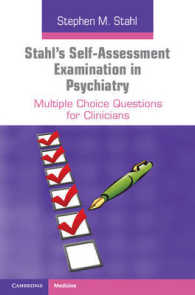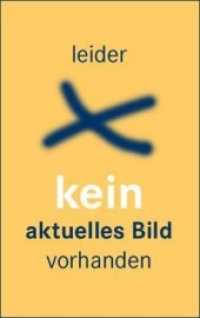目次
序章 レンブラントの世界
第1章 画家への道―1606‐1630 0‐24歳
第2章 栄光の階段―1631‐1641 25‐35歳
第3章 光と影の中で―1642‐1656 36‐50歳
第4章 魂を描いて―1657‐1669 51‐63歳
終章 レンブラントの遺産
著者等紹介
幸福輝[コウフクアキラ]
国立西洋美術館シニア・キュレイター。東京大学およびルーヴェン・カトリック大学(ベルギー)大学院で初期フランドル絵画を学び、その後、パリ国立図書館およびアムステルダム国立美術館で西洋版画史を研究。オランダ・フランドル美術を中心に、多くの展覧会を企画。また、ブリューゲル、レンブラントなどを中心に多数の著訳書がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
375
序章で、レンブラントの生きた17世紀初頭のネーデルラントを「プロテスタントの共和国」と呼んでいる。たしかに、それ以前のカトリシズムに基づいた宗教画と比べるとレンブラントのそれは大きく違っている。例えば、本書の後段で紹介される「聖家族」(1645年)などを見ると、天使こそ空から降りてくるが、その天使にもまた聖母子にも光輪(ニンブス)が描かれていない。天使がいなければ、17世紀の普通の市民の母子にしか見えないのである。「カーテンのある聖母子」(1646年)にしてもそうだ。2021/03/06
ハイク
129
オランダのナショナルギャラリーで代表作「夜警」を観た。中央に飾ってあり国宝扱いで門外不出だという。隣室にレンブラントの数多くの自画像が飾ってあった。これら以外に覚えてない。日本で開催されたレンブラント展を2-3回観たと記憶している。自画像、宗教画があった。「テュルプ博士の解剖学講義」はマウリッツハイス美術館で観た。精巧な描写であった。また銅版画も数多く観た。レンブラントは私の好きな画家の一人である。晩年莫大な借金をしてたとは知らなかった。工房で弟子から年間100-150万円の授業料をとっていたという。 2016/10/10
アキ
86
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン、1606-1669.17世紀オランダを代表する画家。1642年に描かれた「夜警」アムステルダム国立美術館が代表作。しかしその年に妻のサスキアが死去。乳母からの訴訟、破産などに至る波乱に満ちた人生。「My Rembrandt」の映画では、肖像画ヤンシックスから11代目の画商や、ロスチャイルドが1877年に購入し手放した夫婦の肖像画、スコットランドの貴族が飾る本を読む女などが、今でも人々を魅了し続けている様をドキュメンタリーで映し出す。ため息が出る程美しい。2021/03/08
Maiラピ
9
レンブラントはあまりすきになれないのだ・・・もっと時間の経過後に好きになったりするのかな。2011/04/18
koke
8
レンブラントは画業の初期から「光の画家」だったが、年代順に見ていくと光の性質が変わっていくこと。劇的で現代人にも分かりやすい構図には、物語画家のもとでの修行が活きていること。これらの指摘のおかげで、レンブラントの意味不明な凄さの正体がつかめてきた。2022/07/09