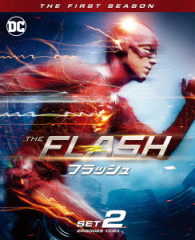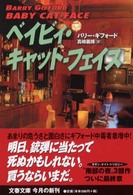内容説明
東山の作品は風景との真摯な対話によって、自身と自然との合一をはかるところに生まれてくる。これもきわめて日本的な考え方とも見えるが、その姿勢は現代において日本人が失いつつあるものである。人間と自然が乖離しつつあるこの時代に、作品を通して自然との対話の大切さを語り続けてきた東山芸術は、その意味で時代に生きる感覚を確かに宿している。東山魁夷の作品が多くの人々の共感を得ているのも、実にそれゆえといえよう。
目次
序章 おいたち・少年時代
第1章 青春の彷徨
第2章 遍歴の山河
第3章 風景開眼
第4章 北欧への旅
第5章 日本美への回帰
第6章 ドイツ・オーストリアの旅
第7章 水墨画の世界へ―唐招提寺障壁画の制作
第8章 おわりなき風景との対話
著者等紹介
尾崎正明[オザキマサアキ]
1948年埼玉県生まれ。早稲田大学文学部美術史学科卒業・同大学修士課程修了。1974年より東京国立近代美術館に勤務、現在同館副館長
鶴見香織[ツルミカオリ]
1969年埼玉県生まれ。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業。1993年より群馬県立近代美術館に勤務。2006年より東京国立近代美術館主任研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
306
こうして通観すると、東山魁夷は日本画と洋画のそれぞれの利点を共に合わせ持っているかのようだ。絵画の技法としては、基本的に日本画。そして構図は時として洋画のそれであったりする。絵から受ける印象もまた単一ではない。魁夷の絵を編年体で見るのは初めてだが、美術学校1年生の時の「南天」からして既に別格である。「栴檀は双葉より芳し」というところか。好きな絵を列挙すると「秋翳」、「白夜行」、「冬華」、「花明り」、「年暮る」、「晩鐘」…。いやもう全くキリがない。そして、あらためて思うのは、色彩の美しさと深みである。2025/03/15
アキ
108
長野県立美術館併設の「東山魁夷館」を訪れた後の復習として読んだ。1945年召集され、熊本で見た阿蘇山の美しさが、景色を見る原体験になっていると感じた。翌年に家族を全員亡くし、47年「残照」・50年「道」を発表し人気画家となった。いずれの作品も東京国立近代美術館にあるが、横浜生まれ神戸育ちにも関わらず、信濃の山を描き、ドイツ・北欧など旅し、北方の厳しい自然に魅かれた。長野では白い馬シリーズを鑑賞した。いずれの絵も端正で抒情的であり、景色が語りかけるように感じる。国民的画家のひとりであることは間違いない。2021/10/21
れみ
54
何度目かの再読。魁夷さんのお誕生日なのでその人生の歩みを中心に読んだ。肉親との別れ、戦争による生命の危機や儚さへの悟り、画業がなかなか日の目を見ない苦しみ。若い頃の様々な苦境が、画家として世に広く知られるようになってからも北欧やドイツ・オーストリアへの旅、山水画への挑戦など、新しいことへ踏み出すしなやかさと強さ、優しさを生んでいるように思えてならないのです。2015/07/08
hit4papa
52
アート・ビギナーズ・コレクションと銘うたれているだけに、入門書としては最適のガイドブックです。ただし、全ての作品が網羅されているわけではないので、作品の鑑賞を主眼とするならば画集に目を向けた方が良いでしょう。本書を読むと、魁夷が90歳まで生涯現役、そして常に成長し続けようとした人物であることが伺い知れます。序章と全8章からなる解説は、魁夷のライフイベントとそれに伴う作風の変化が上手くまとめられています。るほど名を残す画家は、才能を研鑽する努力と成長し続けようとするモチベーションが原動力なのだと分かります。2019/08/27
れみ
45
東山魁夷館訪問後再読。今回観た本制作は「冬の旅」「聖夜」「静かな町」「霧氷の譜」「静晨」。冬の景色を描いた作品が多いので、その空気感に身が引き締まる感じ。そして「霧氷の譜」はずっと観てると吸い込まれそうになる感じがした。この前行った山種美術館で本制作を観た「北山初雪」「年暮る」の習作、あと大好きな「白馬亭」も観られて良かった。この本には今回原画の展示があった「コンコルド広場の椅子」が載ってないからそれは別に読もう。2015/01/26
-
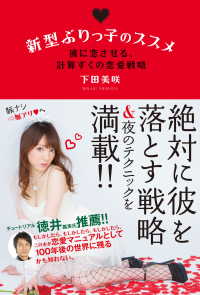
- 電子書籍
- 新型ぶりっ子のススメ 彼に恋させる、…
-

- 電子書籍
- 復讐完遂者の人生二周目異世界譚 1 G…