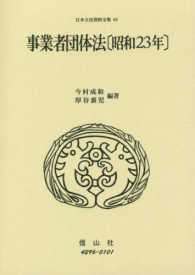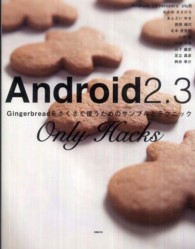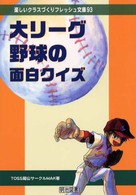目次
第1章 常陸時代―15世紀末~1546(天文15)年頃 誕生~50代半ば頃
第2章 小田原・鎌倉時代―1546(天文15)年以後~1556(弘治2)年前後 50代半ば~60代半ば頃
第3章 奥州時代前期―1556(弘治2)年前後~1562(永禄5)年前後 60代半ば~70代前半頃
第4章 奥州時代後期―1562(永禄5)年前後~1577(天正5)年以後 70代前半頃~86歳以後
著者等紹介
小川知二[オガワトモジ]
1943年、横浜市生まれ。京都大学文学部(哲学科美学美術史専攻)卒業。茨城県立歴史館に主任研究員として勤務していた1992年、同館開催の「新規開館記念特別展 雪村―常陸からの出発」を担当。のち東京学芸大学教授となる。2002年開催の「雪村展戦国時代のスーパー・エキセントリック」(千葉市美術館など4館共催)にも特別学芸協力として関わる。2005年、東京学芸大学を退任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うちだ
5
謎の男・雪村。尊敬する雪舟から一文字もらい、いかにも弟子でございますというムードを出しておきながら、弟子でもなければ画風も全然似ていない。そして表紙のショーシャンクの空に的な絵もわけが分からない。そんなイメージでしたが、読んだ結果、雪村の謎めいたイメージは実際に謎の多い男だからだということが分かりました。ただ雪舟と違って絵は多く残されているようで、さまざまな作品が見られます。変な絵も確かに多いんだけど、雪舟に近い画風の水墨画もあり、何だやっぱり尊敬してたんじゃん、と新しい発見がありました。2024/06/23
rapo
2
一見奇怪な絵だが見るほどに引き込まれ、ユーモラスでさえある。武家の出で画僧であった雪村が、どう生き何を理想郷としていたのか、絵から伝わってくるようだ。雪村展では、表紙の「呂洞賓図」は前期のみ展示で見られず残念。後世の絵師に多大な影響を与えていたとは知らなかった。何か言いたげな自画像も印象的。2017/06/17
takakomama
2
「雪村展」の予習に読みましたが、行きそびれてしまい、残念。雪村については名前さえも知らず、もっと知りたいシリーズで取り上げるくらい有名な人でしょうか。上を見上げている人の水墨画が多かったです。2017/05/21
ヴァンさん@NEWマンガ雑誌の読書会
2
雪村について、知識ありませんので、評価のことを書こうと思います。「はじめに」で、大観2件の重文に対し、6件だよ!ってので、すごいけど、(詳しいことはわかっておらず)雪舟ほど歴史的に価値がつくられてない、って書いてあります。私もわからない。実際、読んでも中国絵画との差異があるのかいまいち謎。同時代・そして後世での評価のつくられ方っていうのが、一つの美術史的な論点になるんでしょうね。。。みたいなことをぼんやりと思いました。著者には申し訳ありませんが、同じく雪村の展覧会を開いた明治学院の山下裕二先生が気になる。2013/08/07
hanya
0
もっと知りたいシリーズ(5)2021/09/29
-
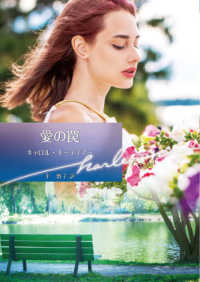
- 和書
- 愛の罠 ハーレクイン文庫