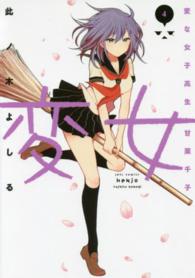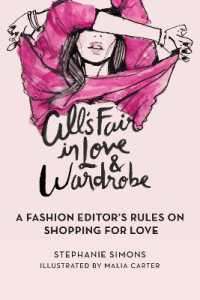内容説明
基礎から構造・設計のマニアックな知識、鑑賞のツボまで、ぎっしり詰まった「城」入門書の新しい定番。
目次
第1章 歴史編(上代・古代の城;中世の山城 ほか)
第2章 建築編(天守の構成;天守の構造1 望楼型と層塔型 ほか)
第3章 土木編(縄張の種類;江戸軍学と縄張 ほか)
第4章 城下町編(城下町の構造;町割 ほか)
著者等紹介
三浦正幸[ミウラマサユキ]
広島大学大学院教授。工学博士、一級建築士。1954年名古屋市生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ポチ
54
200頁弱ですが内容は細部に至るまで物凄く充実しています。巻末の全国名城案内や城に関する索引・用語解説、各ページの下にある注意書きなど、これでもかと親切に教えてくれています。「城に行きた〜い‼︎」今まで見過ごしていた所や気付かなかった所も見つけられ、より楽しく城巡りが出来そうです。城好きな人ならきっと満足する一冊だと思います(^^)2017/02/09
スー
12
写真と図説が沢山のっているのでとても分かりやすい。石垣の写真に見とれてしまいます。熊本城の石垣が見たかったのに残念ですが、見れる日が来るのを楽しみに待ちたい。城下町の構造が一番興味深く楽しめました。城が持てない陣屋大名がいたとは知らなかった。勉強になりました。2017/07/01
mura_ユル活動
10
室町時代に今までの山城から平城へ転換した理由は、戦国大名の巨大化が大きく関係している。山城では増え続ける家臣団を収容する敷地が限られること。その上、強大な戦国大名の軍事力と経済力によって大規模な高い石垣や広い水堀などの人工的な構造物の工事を実施することができたこと。残念なのことは城郭建築の大半は失われ復元されているものもあるが、復元考証は杜撰(ずさん)で偽物のようになっていること(筆者記述)。創意工夫を凝らした城は意匠に富み、城それぞれに特徴がある。近くに寄った際には歴史も踏まえて可能な限り訪れてみたい。2012/08/19
ohmi_jin
5
シリーズ名そのまま「すぐわかる」ではあるが、結構マニアックなことまで書いてあるので、全部をじっくり、というわけにはいかなかった。とはいえ、未だ知らない城もあってやっぱりこの分野は奥深い、と感じた。2021/07/10