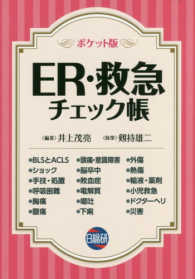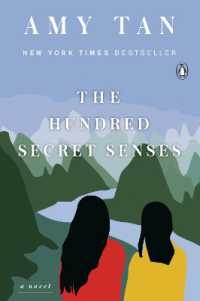目次
序章 いま福島で生きる意味
第1章 福島の惨禍に何を見るか
第2章 憲法の視点から見た原子力災害
第3章 チェルノブイリから何を学ぶか
第4章 電源三法は廃止すべきである
終章 原発とは結局なんだったのか
創作 雨―または逃走譚
「原発いらない!三・一一福島県民大集会」宣言
福島第一原発事故発生からの主な経過
著者等紹介
清水修二[シミズシュウジ]
福島大学経済経営学類教授。1948年東京都生まれ。京都大学大学院経済学研究科博士課程満期退学。専門は財政学・地域論。原発立地を促進する電源三法交付金制度の問題点を指摘し、福島第一原発事故前から原発に批判的な立場をとってきた。2008年4月から2012年3月まで福島大学副学長を務め、原発事故後の対応に奔走。2011年11月には福島県チェルノブイリ原発事故被災地調査団長としてベラルーシ、ウクライナを訪問。2012年3月11日に開かれた「原発いらない!福島県民大集会」では呼び掛け人代表となった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みも
26
現福島大学副学長の著者。福島在住。本当の意味で私事と考えられるのは、こういう立場の人だろう。しかし、「原発事故の責任の1割は国民にある」との意見には承服できない。明らかに歴代政府はリスクを隠蔽し、安全神話なる怪物を造形し、僕達を欺いて来た。雲上人がサクサクと再稼働を推進し、安全より経済の奔流を止められず。人心を分断し、軋轢を生じさせる恐るべき人災。天災とは本質が違う。福島や沖縄の辛苦を、どれだけの人々が思いを同じに出来るだろう。国政選挙を目前に控え、僕らは目を見開いて選択する権利を行使しなければならない。2016/06/20
かわくん
0
「今回の原発事故の責任の一端は国民にある」という指摘はその通りだと思う。原発設置を進める政府、誘致に積極的な地方自治体。それを選んできたのは有権者である国民であり、市町村民である。原発ができて以来、一部の科学者たちは原発や高レベル放射性廃棄物の危険性を叫んできたにもかかわらず、私たちは結果的に原発を容認してしまった。有権者の科学的リテラシーを問うことは簡単だが、経済や政治について政治家や官僚に任せっきりのつけが、今度の震災による事故につながったとは言えないか。私たちはこの事故を契機に、主体的な政治選択の道2012/11/16