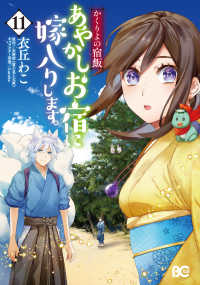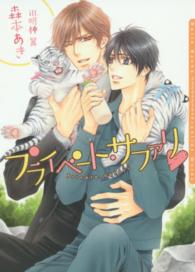出版社内容情報
自分がつくった器で料理を楽しむ、花を活ける……
桐朋学園教育研究所で23年にわたり陶芸の指導をしている著者が、そんなあなたの夢を実現します。
粘土の扱い方から基本作業、形づくりのコツまで、すべてがわかる陶芸テクニック教室。
【書評再録】
●山陰中央新報評(1998年11月24日)=陶芸の基本工程のうち、「形づくり」を中心に、豊富なイラストで解説する。生涯楽しめる趣味の世界へ、その扉を開く助けになるかもしれない。
●文藝春秋「旬の実用書を読む」(1999年1月号)=焼物を始めようとする人の必読書。
【読者の声】
■女性=わかりやすく納得いく内容の本でした。言葉と図柄で表現されていましたので、自分が作業している時を思い出しとてもわかりやすく読ませていただきました。エピローグの中の“形づくりの心構え”と“無垢の行為”を読んで感動しました。その通りだと思います。何度も何度も読み返して心に留めておきたいと思います。良い本をありがとうございました。
【内容紹介】本書「はじめに」より
情報や流通の発達に伴って、やきものの材料、器材、設備などが簡単に手に入るようになったことや、やきものを作りたいという気持ちの高まりから、誰でも自由にやきものが出来るようになりました。また、これまで職人や専門家たちだけのものとされてきた、やきものの世界も開かれ、多くの人が作るよろこびを共に味わえるようになりました。
いままで、手づくりの作品は、作る人それぞれの考え方や方法によって作られてきましたが、本書では、手づくりの陶芸をする人のために、形づくりの作業を、わかりやすく、ていねいに分類、整理して紹介し、粘土の扱い方、形の作り方、やきものの形づくりにおける独特の技術など、形づくり全体を理解できるようにしてあります。
粘土による形づくりは、粘土が徐々に乾いてゆくのに合わせて形を作り、完全に乾燥するまでに作品を仕上げます。形づくりの中で大切なことは、粘土の乾き具合をみて、その時期をのがさずに、必ずしなければならない作業と絶対にしてはいけないことを判断できるようになることです。粘土の乾き具合や硬さは、粘土を見たり、触ったりして見極めますが、それに合わせた作業の判断ができるようになるまでには、時間と経験が必要です。本書の各項目には、粘土の表情をとらえて、10段階のレベルに分類した番号をつけてあります。分類表は著者の長年の経験とデータにより作成したもので、粘土の状態から判断して、作業時期を決めるのに非常に便利です。粘土を扱うときには、いつも粘土がどのレベルの番号に当たるかを思い浮かべるようにしてください。
なお本書は、やきものをしている人や指導する人が、制作中に気がついた点を、忘れないうちに書き留められるように、書き込みのスペースを取りました。制作場所に携帯して、読者自身の形づくりの本、手引き書、テキストとして活用できます。
【主要目次】
▲▲プロローグ
やきものが出来上がるまで/何を作りたいのか、どうしたらうまくゆくのか/基本の道具
▲▲第1章 粘土の扱い
やきものに使う粘土のこと/粘土の表情
▲▲第2章 大切な基本作業
練る(揉む)/撚る/切る/曲げる/伸ばす(引っぱる)/押す/延ばす/叩く/締める/変形する/削る/接着する/解く/養生、乾燥させる
▲▲第3章 形づくりの方法
紐づくり/板づくり(たたらづくり)/型おこし/塊づくり/水びき(ろくろびき)/作り方の併用/自由な作り方/各部の作り方と組み立て/仕上げの技法
▲▲エピローグ
新しい形との出会い
内容説明
30年にわたり、陶芸作家として教えてきた著者が、楽しくできるやきものづくりのツボを全公開。
目次
プロローグ(やきものが出来上がるまで;何を作りたいのか、どうしたらうまくゆくのか;基本の道具)
第1章 粘土の扱い(やきものに使う粘土のこと;粘土の表情)
第2章 大切な基本作業(練る(揉む)
撚る
切る ほか)
第3章 形づくりの方法(紐づくり;板づくり(たたらづくり)
型おこし ほか)
エピローグ(新しい形との出会い)