出版社内容情報
千年におよぶ歴史をもちながら、幻の芸能といわれた猿まわし芸は、どのように伝えられ、今日の隆盛をみたのだろうか。
「周防猿まわしの会」の初代会長として、消えつつあった猿まわし芸を発掘し、はじめて大衆芸能として育て上げた著者が、渾身の力をこめて描き切る、猿まわしの歴史と現在。
【書評再録】
●アニマ評(1992年1月号)=猿まわしの復活を軸に、社会の底辺におかれてきた未解放部落の人びとのたくましさをあたたかく、生き生きと描き出した好著である。
●日刊ゲンダイ評=千年におよぶ歴史をもつという猿まわし芸のルーツを辿り、猿まわしの里と猿まわしたちの苦難に満ちた旅を活写した迫真のドキュメント。
【内容紹介】本書「はじめに」より
猿まわしの旅ゆきのことが一冊の本になるのは、この本がはじめてである。猿まわしは「まぼろしの芸能」と言われ、芸能史の研究で、その歴史的実態をつかみかねている分野である。だから、面白さを狙うあまり、事実や真実から、いささかでもはずれることは許されない。この本は、まぎれもなく、猿まわしの歴史書である。
私が、鬼の首でも取ったように嬉しかったのは、明治中期、高州部落の娘が、親方を保証人にして、役所に出した、小間物行商申請書である。同時に、明治初期、十数人の婦人連名の申請書も出てきた。
この資料を見るまで、私は、猿まわしの歴史は古いが、油売りの歴史は新しいと考えていた。それが、とんでもない見当違いだったということがわかった。さっそく、数人の老人たちに聞いてみると、資料を裏づける談話がとれた。そして、猿まわしは芸能化する条件に欠け、一緒に旅をした油売りの女たちの保護によって、かろうじて命脈を保った事実が浮き彫りになった。この資料が得られなかったら、史実の上で、重大な誤りをおかすところであった。
もう一つ重大な発見があった。猿まわしのルーツがインドであることが明確になったことである。初夏の頃、私は上京した折に、民族文化映像研究所の姫田先生を訪問した。とりとめもない雑談をしている時、姫田先生が「ジロー君の芸を見ていて、ぐうぜん、踊りのような動作をしたのでびっくりしたんですが、あれは教えたんでしょうかね?」と聞く。「そうです。古来から伝わる足どりという芸なんですよ」と私は説明した。「実はインドの猿まわしの踊り芸がまったく同じなんです」と姫田先生は目を丸くした。この一瞬、千年の歴史的な空白が埋まり、インドと日本の猿まわしがドッキングしたである。
このほか、いくつか、幸運だとしか言いようのないかたちで、新史実をつかむことができた。そのことごとくが、この本を書くにあたって、私がほしくてたまらなかった裏付けである。
自画自賛になるようで心苦しいが、この一冊で、まぼろしの芸能と言われた昔の猿まわしの旅ゆきの具体像を描ききることができたと思う。あとは、面白すぎるほど面白いと思われ、読者に読み通していただけたら、それこそ最高の幸運である。
【主要目次】
▲▲第1章・馬あっての猿まわし=武士と馬/馬は人命より尊ばれた/猿まわしの登場/猿舞いの上覧/厩祓い/堕落の一途
▲▲第2章・猿まわしをはぐくんだ里=上下ゆきの拠点/高州の土地と人/毛利の酷政/江戸と高州の猿まわしは同根/明治の部落解放令と上下ゆき/上下ゆきの実態を追う
▲▲第3章・九州上下旅--その1=結婚は男の就職/みよの家庭/年に一度のにぎわい/はじめての旅立ち/下関から門司へ/夜明け前に/戦闘開始/子方の管理術/トロへぎの原価計算/ドカ打ち/ひっかけバタ/初旅の若者たち/小事件/世帯持ちは哀れ/猿と遊廓の女たち/地獄越え
▲▲第4章・九州上下旅--その2=雨の日のねばり込み/ドカ打ちの達人/ぼろをまとった神様/親方の怒り/懸賞で励ます/親方の願い/親方と子方の食い違い/少女の死
▲▲第5章・貧しさのゆえに=猿まわしと正月/おぞ気立つ物乞い/久しぶりの古里/みよの自覚/うそも方便/上下ゆきの道すじ
▲▲第6章・瓢箪から駒=東京の根拠地、押上/夜這い/男と女/思わぬ変身/みごもる/芸人誕生
▲▲第7章・前途多難=仕込師をめざす/立回りの仕込み方/ふたたび東京へ/蛇に見込まれて/盃を一日で返す
▲▲第8章・時代の波=ふたたび九州へ/胎動する気運/ドカ打ちという芸態/水平社の結成
▲▲第9章・戦後の猿まわし名人=若夫婦の旅/芸をぬすむ/ゆきづまり/徹底的な仕込み/新宿駅前でバタ打ち開業/女性の猿まわし/猿、テキ屋を襲う/拳銃に東京を追われる
▲▲第10章・千年の灯が消える=都落ち/人目を引かぬ所で/やくざが土足で
▲▲第11章・不死鳥=一筋の糸/会心の一発/全国から依頼殺到/悲劇を繰り返さぬために/花に託して
内容説明
千年におよぶ歴史をもちながら、まぼろしの芸能といわれた猿まわし芸は、どのように伝えられ、今日の隆盛をみたのだろうか。「周防猿まわしの会」の初代会長として、消えつつあった猿まわし芸を発掘し、はじめて大衆芸能として育て上げた著者が、渾身の力をこめて描き切る猿まわしの歴史と現在。
目次
はじめに まぼろしの芸能の実態
馬あっての猿まわし
猿まわしをはぐくんだ里
九州上下旅
貧しさのゆえに
瓢箪から駒
前途多難
時代の波
戦後の猿まわし名人
千年の灯が消える
不死鳥
感想・レビュー
-
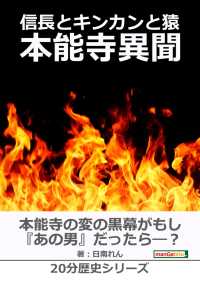
- 電子書籍
- 信長とキンカンと猿~本能寺異聞~ 黒熊…







