出版社内容情報
沖縄の神話・伝説に伝わる創世神アマミクは、どこから来て、何をもたらしたのか。
130余点の写真と論考でアマミクの足跡をたどり、沖縄文化の源流をさぐる。
【書評再録】
●沖縄タイムス評=詩的、文学的想像力をかきたててくれる。
●歴史と旅評=すぐれたフィールドワークの書。
【内容紹介】本書「本文」より
『おもろさうし』に学び、島々の神歌を追って沖縄の各地をめぐるうちに、沖縄の祖先神といわれるこのアマミクが、私の脳裏を去らなくなった。ところが、長い間こだわり続けてきたアマミク神にかかわるフィールドワークだったのに、ここ数年前から、若い頃には視野に入らなかったある一つの景観に気づくようになってきた。
高からぬ丘陵を背にした集落、全面の海に広がるサンゴ礁に囲まれた海幸豊かなイノー(礁湖)、流れ入る小流に沿って拓かれた小規模な耕地(迫田)、そしてそのもっとも奥まったところには神田と聖地があり、小高い丘に囲った住居地をアマグシク、あるいはアマングシクなどと呼んでいる。かんたんにいうと、これが神祭りと神歌を育んだ村々の景観であり、これを私は「アマミクの里」と呼ぶことにした。
沖縄各地で見られる景観であるが、これが「アマミクの里」の構造としてはっきり私に迫ってきたのは、沖縄本島北端の辺戸、西海岸に出ばった本部半島の突端備瀬と半島の付け根の屋我地島周辺、国頭村の奥間・比地を訪ねた時であった。
奥間ターブックワ(田圃)は、北部西海岸の大きな稲作地帯であった。辺戸岬から本島西海岸を南下していくとき、最初に突き当たるのが奥間の西方に出ばったアカマル(赤丸)崎の突起である。西海岸沿いにここに辿り着き上陸した往古の人々は、鏡水の浜にかけてのイノーを海の畑、すなわち生活空間として活用しながら、比地川を辿って流域に稲作地を拓いていったと思われる。比地川を遡った突き当たりの小高い杜をアマングシクという。アマミクの造ったグシク(生活跡地)の意であろう。
さらに、奥間・比地では、稲作を伝えた神の名をアマミクと伝承している。アマングシクの南側には神が天降りをする小玉杜という御嶽があり、海とかかわりの深い神祭りのウンジャミ(海神祭)が営まれる。小玉杜のすぐ脇にはアマミクの宮(通称山口神社)があり、その南斜面を降りていくと、ミルク田と呼ばれる神田がある。集落の伝承は、そこでアマミク神が集落の長老に稲作を伝授したと伝えている。比地の村芝居で語られるユングトゥ(誦み言)は、耕地を拓いて行なう稲作の手順を季節を追って述べ、神酒をかもして神祭りをするという内容で、豊穰予祝の神歌の典型である。奥間・比地集落には、祖神アマミクの記憶がきわめて鮮やかに焼きつけられているのである。
【主要目次】
▲▲序---正史にみるアマミク神
祖神アマミクとは/アマミク神の足跡(東海岸への道)/アマミク神の足跡(西海岸への道)/日本列島各地にもみられる海人の里/地名にみる海人と稲作の道/複眼的にみる沖縄文化
▲▲第1章 アマミクの里
奄美大島・阿摩美姑神社の石碑/奄美大島・笠利町のアマンデーと節田集落/奄美大島・笠利町辺留の海岸/奄美大島・笠利町の宇宿貝塚/奄美大島・笠利町の安良川・アラホ河口/奄美大島・龍郷町秋名の平瀬マンカイ/奄美大島・平瀬マンカイのノロ(神女)たち/奄美大島・龍郷町秋名のショッチョガマ/奄美大島・龍郷町秋名の高倉/奄美大島・秋名のコスクとテンツ(天津)山/与論島の赤崎海岸/与論島の赤崎御願/赤崎海岸のイノー/与論島のシヌグモー/久米島のオー(奥武)島とオーハ/久米島東海岸からみるオー島/久米島アーラ岳と御穂田/久米島のアーラ御嶽/久米島の仲地の水田/久米島の具志川城跡(具志川御嶽)/奥間のアマングシクと比地川/奥間のアマングシクの頂上におかれた海石/奥間の稲作地帯/比地のミルク田(神田)にある井泉/比地のウンジャミ(海神祭)/比地のウンジャミにおける鼠送りの儀礼
▲▲第2章 沖縄本島西海岸を渡るアマミク
伊平屋・伊是名の島じま遠望/伊平屋島北端のクバ山/伊平屋島のクマヤガマ(洞穴)/伊平屋島田名のターブックワ/伊平屋島の片隈御嶽と我喜屋の稲作地/伊是名の降神島/伊是名グシク(城跡)/伊是名島の陸ギタラ・海ギタラ/伊是名島諸見の稲作地/具志川島/伊江島のグシク山とグシク御嶽/伊江島の具志原貝塚/伊江島の阿良御嶽/伊江島の宮寺御嶽/伊江島の富里拝所跡/伊江島の新富里拝所/アマンユー(海)/本部町備瀬崎とミーウガン/本部町備瀬のイノー/本部町備瀬集落の神アシャギ/満名川岸にあるアマシガー/本部町伊野波の神田にある拝所/本部町伊野波御嶽のイビ/伊野波の神祭りシヌグの中のムックジャー/伊野波の祭祀舞踊ウスデーク(臼太鼓)/名護市の宇茂佐御嶽(アヲヤマの御嶽)/屋部川の河口/名護市屋部の渡波屋/屋部を流れる新波川とアッパハー/羽地内海の奥武島/羽地内海のジャールマ/屋我地島のアマグシク/今帰仁村の古宇利島/今帰仁村の大井川流域/今帰仁村の天底集落
▲▲第3章 沖縄本島東海岸を渡るアマミク
辺戸の安須杜/辺戸のアマングシクと迫田跡/辺戸岬と宇佐浜海岸/辺戸の神アシャギ/辺戸の宇佐浜遺跡/奥集落と奥川/アラハ(安田ガ島)/安田川流域と安田集落/安田の神アシャギ/安田のシヌグのヤーハリコー/安田のシヌグの田草取り/名護市安部のオール/伊波グシクからのぞむ石川市全景/伊波グシクのイシヌイビ/伊波グシク崖下の天願のアブ(岩の割れ目)/石川市嘉手苅の前のティラ/石川海岸の赤崎/具志川市の具志川グシク/具志川市のアカジャンガー(赤山川)遺跡/宮古島東南海岸の赤崎御嶽/浜比嘉島のシルミキヨ洞/浜比嘉島のアマミキヨ墓/平安座島のシヌグモー
▲▲第4章 歴史のあけぼの---王国神話への登場
久高島久高島の伊敷浜/久高島の蒲葵御嶽/神祭りの行なわれる御殿庭/久高島のカベール/久高島から知念・玉城に渡るアマミクたち/ヤハラヅカサから久高島を拝む/玉城村の浜川御嶽/玉城村のミントゥングシク/知念村の知念杜グシク/玉城村の玉城グシク/玉城村百名の受水走水/斎場御嶽1--拝所の三庫裡/斎場御嶽2--御嶽内の鍾乳石と聖水/斎場御嶽3--三庫裡から久高島を望見する
▲▲第5章 アマベ(海人族)の足跡
伊勢の志摩半島/志摩半島の大王島/青峰山と青ノ峰信仰/伊雑宮の御田植祭--清めをうける海女たち/伊雑宮の御田植祭--竹取神事/伊雑宮の御田植祭--御田植神事/丹後半島伊根の舟屋/丹後半島伊根町の青島/若狭湾口の大島(冠島)/京都上賀茂の大田神社/大田神社の末社--百大夫社/鳥取県米子市の粟島神社/出雲の阿太加夜神社の荒神祭跡/出雲の揖夜神社/揖夜神社末社の荒神社/出雲の意宇川流域/山口県萩市の阿武川/山口県阿武郡大井川流域の稲作地/山口県阿武郡の大島/山口県阿武郡大島のアカホの水田/山口県阿武郡大島地内のテラヤマ/韓国江陵市の端午祭/江陵端午祭のチャンジャマリ/韓国江陵市江門洞の海神洞と瓦屋根/長崎県壱岐島の古墳/長崎県壱岐島の稲作/速水瀬戸(豊予海峡)と高島/大分県臼杵の海辺村/大分県の臼杵神社(アマベの里)/大分県臼塚古墳の石棺/大分県南海部郡の大島と桑の浦のアコー木
内容説明
沖縄の祖神アマミクは、どこから来て何をもたらしたか。はるかな海上の道をたどって、オー(小島)を足がかりにウフヂー(大地)に上陸し、生活空間を拓いたアマミクの足跡を辿り、沖縄文化の源流を探る。
目次
序 正史にみるアマミク神
1 アマミクの里
2 沖縄本島西海岸を渡るアマミク
3 沖縄本島東海岸を渡るアマミク
4 歴史のあけぼの―王国神話への登場
5 アマベ(海人族)の足跡
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナディ
J_L_B_459
-
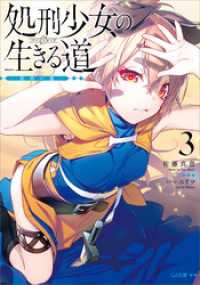
- 電子書籍
- 処刑少女の生きる道(バージンロード)3…








