出版社内容情報
敗戦の焦土の風景が残る1949年夏に起きた政治謀略。
戦後日本の歴史をねじ曲げたのは誰か。
今もって多くの謎を秘めている奇怪な事件の真相へとせまる。
【各氏絶賛】
■山田太一氏(シナリオ作家)=ドキドキしながら読んでいます。あの時代がなまなましく蘇って、とにかく面白いです。
■黒田清氏(ジャーナリスト)=この本を手にした夜は朝がた近くまで眠れなかった。若い夢追い人よ、この本を読んでジャーナリズムの門を叩いてくれ。
■樋口恵子氏(評論家)=当代一流のジャーナリスト斎藤さんが、時代の水先案内人として警鐘を鳴らしつづけた作品を通読すると、さながら被治者の側から見た戦後通史の観がある。
■松本清張氏(作家)=その寝食を忘れた熱意と、精力的な追及心と、工匠を思わせるような取材技術とは、最近とかくマンネリ化したといわれる新聞・雑誌記者を奮起させるであろう。
【書評再録】
●朝日新聞評=ジャーナリストとして生きた著者の深いエートスが、詩的に、しかし剛直に表現されていて、心を打たれる。
●三田評論(内海愛子氏)評(1991年1月号)=克明に取られた取材ノート、短い記事の裏につぎ込まれた情熱、社会的弱者への温かい眼差し、権力犯罪への怒り--時に応じて見せるジャーナリストのこころの動きが読みやすい文章の中から浮かび上がり、多くの時間を経過した今も読む者の心を打つ。すぐれたジャーナリストが、たぎるおもいで書き綴ったこれらの書を読み終えて、深いため息とともに自分の過去を振り返る人も多いだろう。
【内容紹介】本書「まえがき」より
口はばったい言い方になるのを恐れずに申し上げれば、私なりに、この「取材ノート」に収録した文章には、ひとつひとつ深い思いがかかっており、どの行にも愛着がある。
もともと私は、東京に本拠を置く報道機関で働いていた。記者という職にありついて、はじめてその職場に出掛けていったとき、机の上にずらりと並んだ電話の受話器が、まっ黒な生きもののような不気味さで、ひっきりなしに鳴りわめいていた。
その騒然とした空気に圧倒されながらも、いちど味を覚えてしまうとやめられない秘薬を口にしたかのように、その日から私は「記者たちのいる職場」の、不思議な魅力にとりつかれてしまったらしい。
いささかコッケイな錯覚にすぎないのだが、この職業は絶えず「未来という瞬間」に紙一重の最先端で接触しているのだ、という緊張感があって快かったのだろうか。記者であれば当然のことだが、コトが起こればきまって現場へ飛び出していく。そのたびに、「時代そのもの」にもっとも近い現場で、この手で触れているのだというナマナマしい躍動感が迫ってくる、その快さのせいだったのだろうか。いらい三十数年、人生の大部分を記者という仕事に没入して過ごしてしまった。
この「取材ノート」5巻に収録した文章は、その記者生活の中で、私が右から左へと軽く受け渡してしまう気になれず、記者の業務としてというよりもむしろ、私個人のこだわりで追い続けけたテーマ---謀略・冤罪・天皇・高度成長・労働・子ども・女性・家族・性・生命そのほか---についての、取材体験エピソードをまじえての報告である。
今回、この本をまとめるに当って書き下ろした部分もあるが、多くはかつてそのテーマに真向かっていたときに、新聞用の記事や雑誌原稿として書いたものだ。それらを狂言回し役である私の道案内で読み継いでいただく趣向である。
消えかかった踏み跡を復元するように、およそ三千枚ほどの古ぼけた記録をつなぎ合わせ、脈絡をつけ、できるだけおもしろく読んでいただくにはどうしたらよいか、ないチエをしぼった。その結果、まずそれらの中から半分以下を捨てて、全体をスリムにしたうえ、一巻から一応年代を追って配列しながら、同時にあまり厳密に時代区分をせず、テーマごとのかたまりを見せるように工夫してみた。
さて、こうして編んでいくと、歩いてきた道筋の向こうに、おぼろげながら戦後の「昭和」が姿を現わしてくるように、私には思えた。というよりも、戦後の「昭和」という時代を忌避し続けている私がそこにいる、と言った方が適切なのかもしれない。
私の少し前の世代までは、青春まっただ中にあの戦争に狩り出され、無残に命を奪われた。そのすぐ下の弟の世代に当たる私のような者には、その命たちへの哀惜の情がひとしお強いせいだろうか、あの敗戦からきょうにいたるこの国のありように、いつまでも拒否感がある。戦争の大きな犠牲のあとに目ざした社会はこんなはずではなかったではないか、という無念さと言ったらいいだろうか。いつまでも現世になじめず、その抵抗感を支えにして生きているようなところさえある。あの意地悪い“影の声”に抗して、恥をしのんででもこの「取材ノート」をまとめることにしたのも、ひとつにはそんな昭和ひとケタのひとりの男の胸中にたぎる、執念深い「否!」の声を遺しておきたいという思いからである。
さて、それでは、まず敗戦の焦土の風景が残る1949年夏からご案内することにしよう。
【主要目次】
▲▲第1章 1949年夏の謀略
▲事件前夜(“影”への執着/虚無の匂い/情報の司祭/ドラマの舞台/不気味な序幕/轢断したのは死体だった)
▲他殺派記者は追跡する(法要は“他殺”の日に/23人の目撃者/替え玉に同伴した青年?/的外れの気負い/付着していた油の謎/捜査陣の崩壊/四万字の機密文書/物質が物語るもの/権力者に邪魔な部分/果てしない旅)
▲“下山病”にとりつかれて
▲松川事件はなぜ起きたか(暑い夏・闘いの夏/強引に世論を誘導する/長い日照りが終わって/民主主義の体験/英文の怪文書/草の根をわけても真実を/「自首の日近く」/奇妙に符合する/公判廷で赤面した私/米情報機関浮かぶ/工作者たちの影/お手伝いさんは殺されたか?/“同一人物”からまた)
▲交錯する黒い糸---下山新情報を追う(奇妙なハガキ/替え玉がいた/靴は物語る/ある朝鮮人/日本の検察調書がGHQ文書にあった/供述調書めぐる疑問点/李の供述調書/布施元検事総長と一問一答/奇妙な名刺)
▲▲第2章 いとおしい日本
▲友よ! みていたまえ---安保の波のなかで(地下水が大河になるとき/院内に警官隊入れ強行採決/わき起こる反撃の波/ハガチー事件転回点に/6・15流血の日)
▲やがて飽食の迷路へ---日本のなかのベトナム戦争(“参戦国日本”を追って/人間の荒廃と破壊進む/戦争加担の見えない手/犯意なき犯罪者なのか/逃げ出したさそり)
▲▲第3章 ジャーナリストとは何か
▲「記者になる」ということ(衝撃的な出会い/消えた警察官/尾行と張り込みと/警官を尋問する/内部爆破だった/力あるものの情報は疑え/事件が起きた時代状況/本質は何か/壁といわれた少年と教師/通行人のように/金属バット事件の真実/縦軸と横軸)
▲夢追い人よきたれ!(敬遠したい“指示待ち人間”/エセ優等生は困り者/謙虚な人柄こそ望ましい)
内容説明
1990年代、謀略からセックス状況まで日本腐蝕の根源をえぐる。『妻たちの思秋期』『父よ母よ!』の著者斎藤茂男がジャーナリスト作法を公開。
目次
日本地下帝国(黒い蜜の物語;幻の大疑獄―知りすぎた男との会見記;繁栄の暗部;この栄華;戦後社会の毒素)
いまジャーナリズムで何が問題か(本多勝一記者との対話;幻想に酔った日々;仕事場の朝;構造事実)
ミッチーからXデーへ(「現代シンデレラ物語」をめぐって―ミッチーブームの裏側;日本人横井庄一の証言;天皇の赤子の絶望と日本人;天皇とメディア;象徴天皇制で大論議を!)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
午睡
Ted
-
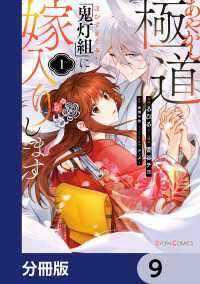
- 電子書籍
- あやかし極道「鬼灯組」に嫁入りします【…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢(ラスボス)の友人ですが、隠し…
-
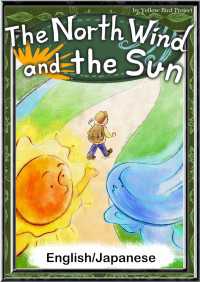
- 電子書籍
- The North Wind and …
-

- 電子書籍
- The Hawaii's Best R…





