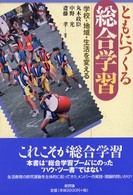出版社内容情報
「多自然型の川づくり」のために必要な河川の環境とそこにすむ生物たちを知るための格好のテキスト。
人工化が進んだ日本の水辺環境を甦らせる河川環境調査の基本書でもある。
【内容紹介】本書「補訂版への監修者の序文」より
本書はもともと「生態学研究シリーズ」の一巻として1971年に刊行され、そのあと版を重ねてまいりましたが、ここ数年は品切の状態が続いておりました。しかし最近になって復刊の要望が強いので、その要望にこたえて復刊をすることになりました。
20年も前の本をという感じをおもちの方もありましょうが、河川の生態学についてこのようによくまとめられた本はその後もでていません。一方において、その後、河川の環境問題がぞくぞくとあらわれ、本書に記されているような河川環境と生物群集に関する基礎的な知識の必要性が痛感されるようになってきました。
水の文化情報誌といわれる「Front」の1990年5月号に私は「川を守るとはどういうことか」というエッセーを書いたことがあります。上高地の梓川で洪水防止のためにいくつもの堰堤を作ろうという案がおこったのですが、上高地の特色ある景観を作っているケショウヤナギやハンノキの林は氾濫原の植生ですから、コンクリートの護岸と堰堤で固めてしまえば上高地的景観はやがて消滅するであろう、というのがその一つの内容でした。
また私の住んでいる千葉県のあちこちの小河川に住んでいた国の天然記念物のミヤコタナゴが最近絶滅に瀕しています。環境庁が編した「日本の絶滅のおそれのある野生生物、脊椎動物編」にものっており、「栃木県、千葉県、埼玉県にわずかの生息地を残すだけとなった」と記されています。
水田の間にちょろちょろと流れているような小川に、かつてはふつうにみられたものですが、マツカサガイなどの二枚貝に卵を産みつけて繁殖するので、これらの条件を充たすところでないと棲めません。ところが、農業生産を高めるための農業構造改善事業に伴って、水路の直線化ないしは人工河川へのつけかえ、洪水防止のためと称して、小川の場合でもコンクリート三面ばりで、少なくとも120センチメートルの垂直の側壁をつけることなどで、ミヤコタナゴは生息できなくなってしまいました。ここには二つの、私が経験した例をあげるにとどめますが、長良川の河口堰など多くの問題が未だに解決をせずに尾を引いています。
本書が、河川生態の問題に関心のある多くの方々に少しでもお役に立てば誠に幸いだと思います。
【主要目次】
▲▲第1章 河川環境とその調査法
▲1.河川の概要(河川の分類/川の形態区分)
▲2.環境調査法(勾配図の作成/調査地点の概観/測定)
▲▲第2章 底生生物の生態学的研究
▲1.河川の底生生物をどう調べるか
▲2.河川の底生生物研究の基礎(生物群集構成員/生活史の研究/世代数)
▲3.河川の生物群集の生態(分布の研究/現存量と生活形/遷移と極相/流下・溯上と産卵飛行/食性と食物連鎖)
▲4.河川生態系の生物生産力(生物生産の概念/摂食量・排出量と呼吸量/羽化昆虫の量と周期性/生物生産量の推定と回転率)
▲5.河川の汚濁(無機汚濁と有機汚濁/生物学的水質判定)
▲▲第3章 魚類の生態学的研究
▲1.川魚の調査法(観察/採集と保存/同定と測定)
▲2.生活史の研究1--産卵と発育(産卵生態/発育の生態)
▲3.生活史の研究2--生長と食性(生長/食性の変化)
▲4.生長の研究(年齢形質による推定/鱗による年齢査定法の限界/連続採取法による推定/季節変化のパターン/上流と下流)
▲5.食性の研究(消化管内容物の調査法/日周変化/季節変化/上流と下流)
▲6.分布の研究(流れに沿って/河床型と分布/地理的分布に関する問題)
▲7.河川の人為的変化と魚類群衆の変遷(人工湖(ダム湖)の影響/水質汚濁の影響/河川改修/アユ型河川からオイカワ型河川へ)
▲▲第4章 河川生物群集の相互関係--その問題点と展望
▲1.藻類と底生動物との関係
▲2.底生動物の被食量をめぐって
▲3.魚、食うものの側から
内容説明
「多自然型の川づくり」のために必要な河川の環境とその生物たちを知るためのテキスト。人工化が進んだ日本の水辺環境を甦えらせる河川環境調査の基本書。
目次
1 河川環境とその調査法
2 底生生物の生態学的研究
3 魚類の生態学的研究
4 河川生物群集の相互関係―その問題点と展望