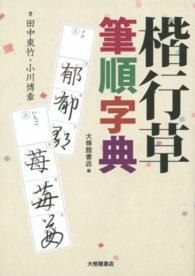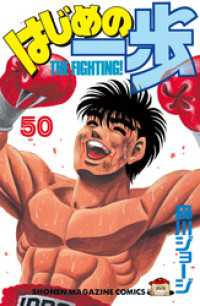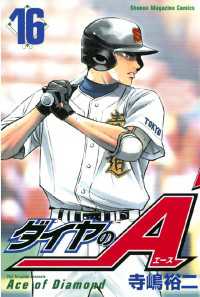出版社内容情報
1,000キロ先まで届くクジラの歌、
対ミツバチ警戒音を持つゾウ、
孵化する前から親子で呼び交わすカメ、
人間の産業活動が発する音で傷つくタコや海草……
ヒトには聴こえない音を聴き取り、意味を解析する研究が進んでいる。
その結果、動物の交流における音声の役割に加え、
聴覚器官を持たない植物やサンゴまでもが音を頼りに活動していることがわかってきた。
デジタル音響技術が明らかにした動植物の知られざる生態から、
人間の経済活動が発する音に影響される陸上・海中の生態系まで、
生命が奏でる音の多様性と未来を描く。
内容説明
1,000キロ先まで届くクジラの歌、対ミツバチ警戒音を持つゾウ、孵化する前から親子で呼び交わすカメ、人間の産業活動が発する音で傷つくタコや海草…。ヒトには聴こえない音を聴き取り、意味を解析する研究が進んでいる。その結果、動物の交流における音声の役割に加え、聴覚器官を持たない植物やサンゴまでもが音を頼りに活動していることがわかってきた。デジタル音響技術が明らかにした動植物の知られざる生態から、騒音公害が陸上・海中の生き物に与える影響まで、生命が奏でる音の多様性と未来を描く。
目次
第1章 生命の音
第2章 海は歌う
第3章 音のない雷鳴
第4章 カメの声
第5章 サンゴ礁の子守歌
第6章 植物たちのポリフォニー
第7章 コウモリのおしゃべり
第8章 ミツバチ語の話し方
第9章 地球生命のインターネット
第10章 命の系統樹の音に耳を傾ける
著者等紹介
バッカー,カレン[バッカー,カレン] [Bakker,Karen]
ブリティッシュコロンビア大学の教授。研究対象は、政治経済学、政治生態学、環境研究、STS、デジタル地理学など多岐にわたる。ローズ奨学生としてオックスフォード大学で博士号を取得したほか、キャリアを通じて、アネンバーグフェローシップ(スタンフォード大学)、グッゲンハイムフェローシップ、ラドクリフフェローシップ(ハーバード大学)など、数多くの賞を受賞した
和田佐規子[ワダサキコ]
岡山県の県央、吉備中央町生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。夫の海外勤務につき合ってドイツ、スイス、米国に、合わせて9年滞在。大学院には、19年のブランクを経て44歳で再入学。専門は比較文学文化(翻訳文学、翻訳論)。現在は首都圏の3大学で、比較文学、翻訳演習、留学生の日本語教育などを担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
たまきら
助作
Micky
げんさん