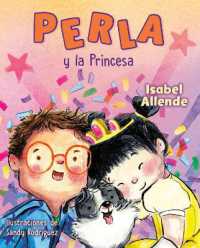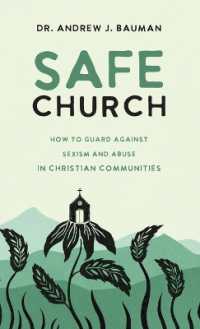出版社内容情報
虫が苦手な人こそ読んで欲しい、虫が愛おしくなる一冊!
なぜそこにいるのか?
なぜその姿をしているのか?
なぜそのような行動をとるのか?
身近な虫もレアな虫も、小さな体にきらめく進化の妙。
むずかしくはないが深い話、知る人ぞ知る虫知識を、
世界的なザトウムシ研究者が虫への愛情たっぷりに紹介。
生殖・分布・形態のふしぎに魅せられる、
人生をちょっとだけ豊かにする虫のトリビア60話。
内容説明
なぜそこにいるのか?なぜその姿をしているのか?なぜそんなことをするのか?アリジゴクの勢力争い、ザトウムシの地理的変異、トンボの翅色多型、ゾウムシの口吻、チョウの交尾栓、クモの円網―。身近な虫もレアな虫も、小さな体は進化の結晶。人に話したくなる虫知識を、世界的なザトウムシ研究者が虫への愛情たっぷりに紹介します。虫好きな人も苦手な人も、多様な進化のふしぎに魅せられる虫のトリビア60話。
目次
4月(交尾栓―ギフチョウ;単独性から真社会性への移行を示すハチ―ホクダイコハナバチ ほか)
5月(巣穴の攻防―ハマベウスバカゲロウ;同胞種間の繁殖干渉―ナミテントウ ほか)
6月(東亜・北米東部型隔離分布―マメザトウムシ;鳥取県東部で変わる翅色二型―アサヒカワトンボ ほか)
7月(名の由来はロシア人女性―エリザハンミョウ;氷ノ山で見つかった分布南西限の集団―ルイヨウマダラテントウ ほか)
8月(随時給餌をするハチ―ニッポンハナダカバチ;千代川と日野川で変異―アカサビザトウムシ ほか)
9月(『砂の女』とハンミョウ―カワラハンミョウ;東亜・北米西部型隔離分布―ダイセンニセタテヅメザトウムシ ほか)
10月(奇跡の発見―オオナミザトウムシ;急速分布拡大の外来種―キマダラカメムシ ほか)
11月(コモンでない古文書のクモ―イヨグモ;二同胞種が混在―ヨモギハムシ ほか)
12月(鳥取市固有のヤスデ―コヤマホラケヤスデ;名にバイデンがつくザトウムシ―バイデントロフス・バイデンス ほか)
1月(亜種から種に昇格―ハイイロフサヤスデ;鳥取県人ゆかりの冬のクモ―ダイセンヤチグモ ほか)
2月(絶食して越冬―オオヒメグモ;雪上を歩く―クモガタガガンボ ほか)
3月(イラガとの攻防?―ヒロヘリアオイラガ;最強生物―ドゥジャルダンヤマクマムシ ほか)
著者等紹介
鶴崎展巨[ツルサキノブオ]
1956年、愛媛県松山市に生まれる。広島大学理学部生物学科動物学専攻卒業(1978年)後、1984年に北海道大学大学院理学研究科博士課程(動物学専攻)修了。理学博士。1987年より2021年3月まで、鳥取大学教育学部助手、助教授、地域学部教授などを経て、農学部教授。この間、鳥取大学附属中学校校長(2015~2019年)を併任。鳥取大学名誉教授。専門分野は動物分類学・動物生態学・集団細胞遺伝学で、おもにザトウムシ類の分類・地理的変異・染色体などを研究するかたわら、山陰地方の動物相調査や鳥取砂丘の昆虫の保全などにも従事した。日本蜘蛛学会会長(2006~2012年)、烏取県生物学会会長(2003~2020年)、日本分類学会連合代表(2012~2013年)。日本土壌動物学会学会賞(2015年)、日本動物分類学会学会賞(2020年)、染色体学会学会賞(2023年)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金監禾重
Go Extreme
Yoko O
lyrical_otoca
-
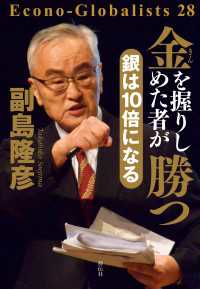
- 電子書籍
- 金を握りしめた者が勝つ 銀は10倍になる