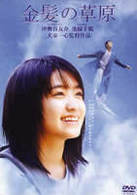内容説明
鳥を巡るタイムマシンの旅に出よう。海に囲まれた日本列島には、どのような鳥類が暮らしてきたのか、そして人間とどう関わってきたのか。化石や、遺跡で出土した骨や土器、江戸時代の博物図譜や現代の野外調査、人の経済活動が鳥類に及ぼす影響まで、時代と分野をつなぐ新しい切り口で描く。
目次
1 骨や遺伝子から探る日本の鳥(化石が語る、かつての日本の鳥類相―太古のバードウォッチング;遺伝情報から俯瞰する日本産鳥類の歴史;考古遺物から探る完新世の日本の鳥類)
2 文化資料から探る日本の鳥(絵画資料からみる江戸時代の鳥類―堀田正敦『観文禽譜』を例にして;文献史料から鳥類の歴史を調べる―ツルの同定と分布の事例)
3 人と鳥類の共存に向けて(全国的な野外調査でみる日本の鳥類の今;人類活動が鳥類に及ぼす間接的影響から今後の鳥類相を考える)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
76
「歴史学」側でなく「生態学」寄りの図書である。まず太古の日本で発見された、鳥の先祖と見られる鳥類類似恐竜の化石の出土状況から始まる。考古遺跡から出土する鳥類骨の分析、江戸期の博物学的研究から再現した国内の鳥類の生息域分布。そして、鳥類分布状況全国調査による、ここ40年の森林相の変遷に影響を受けた鳥類についての研究。そして、現在の鳥類が置かれている状況まで広く見た一書である。案の定、博物学的研究史料の利用では、現代の和名と異なっていて同定が難しいかったものの、現在では飛来しない鶴の飛来が有ったこと2022/03/02
hal
15
日本の鳥について、考古学・歴史学からのアプローチでわかった事や、鳥類学の現状をまとめている。鳥類の研究はなかなか大変なようで、他分野との協力もこれからのようです。文献から過去の日本の鳥類の記述を調べようにも、古文書は素人には書いてある内容が読めないし理解できない。書物化されたものでも、膨大な史料のどこに鳥に関する記述があるか見つけるのが大変というのは、古文書を読む大変さが身にしみている私にはよく理解できます。風力発電や太陽光発電が野生動物に悪影響を及ぼしているという話はショックでした。2021/04/07
めめ
3
鳥類が好きなので鳥の本は何でも読みたい。鳥の化石などを調べてる人の本。世の中色んな人がいるなあと感心した。鳥は、昆虫ほど多くなく哺乳類ほど少なくない扱いやすいサイズ、というのがナルホドと思った。江戸時代の図譜、観文禽譜かんぶんきんぷ、というのがあるのを初めて知った。本草綱目と観文禽譜、いつか読んでみたいというか見てみたい。鳥の絵が迫力あって楽しい。弥生時代には鶏は食べるためではなくステータスだったという話も面白かった。読むのが難しくて時間かかったけど面白かったです。2021/07/30
Tomozuki Kibe
2
江田真毅門下で学びたいという生徒がいるので読む。考古学→考古鳥類学。というニッチな学際研究。内容、鳥類の骨の調査から当時の生活を「妄想」・遺跡の調査から鳥類学に新見解。前者として、弥生遺跡から出る鶏骨の少なさ・雌雄の偏りから「夜明けを告げる鳥」の伝説とともに大陸から「生ける威信財」として来た説を提唱し、後者はアイヌ遺跡の調査からアホウドリの中にはもう一種含まれていたことを立証。鳥と考古学が好きならたまらないだろうし、また学制的に生物学の研究手法も学ばせてばならないが、先駆者が道を拓いてくれているんだ頑張れ2025/11/10
よしあ
1
まとまりのない内容だなあと思った。 あとがきと前書きが逆の方がよかったかも。2022/02/07



![Comic REX(コミック レックス) 2017年2月号[雑誌]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0382699.jpg)