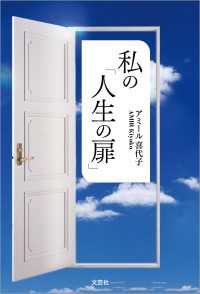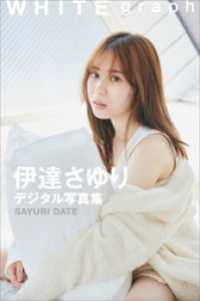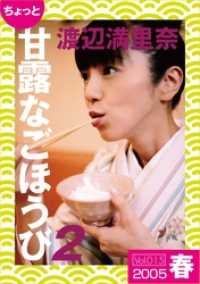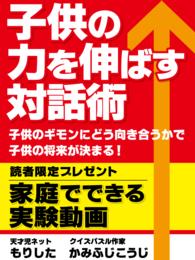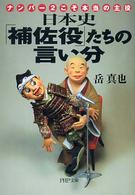内容説明
手つかずの森にたたずむ老樹と会い、その声に耳を傾けた。長年にわたって北海道・東北の森で暮らし、研究を続けてきた著者が語る、身近な樹木の知られざる生活史。森をつくる樹木は、どのようにして生き延び、種の多様性を生み出しているのか。種子発芽のシグナルや種子散布に見る棲み分けと共存、種ごとに異なる生育環境や菌類との協力、人の暮らしとの関わりまで、日本の森で見られる12種の植物を生育場所で分類し、120点以上の緻密なイラストとともに紹介する。
目次
第1章 川辺に生きる(ケヤキ―欅;サワグルミ―沢胡桃;カツラ―桂;オノエヤナギ―尾上柳)
第2章 老熟した森で暮らす(ブナ―山毛欅;チマキザサ―粽笹)
第3章 林冠の撹乱を待つ(ノリウツギ―糊空木;コブシ―辛夷;キハダ―黄檗;アカシデ―赤四手)
第4章 人里近くで生きる(コナラ;ヤマナシ―山梨)
著者等紹介
清和研二[セイワケンジ]
1954年山形県櫛引村(現鶴岡市黒川)生まれ。北海道大学農学部卒業。北海道林業試験場で広葉樹の芽生えたばかりの姿に感動して以来、樹の花の咲き方や種子散布の観察を続けている。近年は天然林の多種共存の不思議に魅せられ、戦後開拓の放棄田跡に天然林を模して木々を植えながら暮らしている。現在、東北大学大学院農学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
53
趣味は焚き火、野生の食物の採取と栽培という大学の先生が、主として北日本の山々で見られる11種類の広葉樹と粽笹について、生態と繁殖の方法、種子から成木になるまでの過程を、長年の研究成果に基づいて記す。それぞれの樹木には著者とともに実践を重ねる研究者がいて、その動静がつぶさに記される。我々が生活の中ではただ木と一括りにする樹木が、このような多様な生き方をしていることに驚かされる。その生き方を何十年という単位で黙々と追いかけ、記録し、森林がより豊かな存在となるべく努力している研究者の営為に頭が下がる思いである。2022/06/28
ユ-スケ
6
数種の木を取り上げて、その繁殖方法や生態について語る まこと驚くべき方法でそれらは生を繋いでおり、植物へのリスペクトを抱かずにはいられないと思うのだがどうだろう こうした観察を長年続けてきた著者をうらやましいと思うともに、その努力に頭が下がる ごくごく単純に、おもしろいですっ!2021/04/22
ジコボー
5
一つのモノを記録し続ける、それを何十年も続けるという事はとてつもない事なのだと思います。まさにライフワーク。緻密に描かれたイラストと観察眼、最初から最後までとても楽しくページめくれました2019/12/22
林克也
3
清和さんの絵が良かった。そして、好きな研究を思う存分することは何ものにも代え難い幸せだと思った。清和さんをはじめとして、この本に名前のあがっている研究者や院生たち、本当に羨ましい。(今の世の中にのさばる、好きな金儲けに邁進する人たちのことは全く羨ましいと思えませんが) 樹も我が子の生存・成長に“こころ”を砕いてあれこれ手を尽くしているということに感慨深いものがあった。 山に行って老木、巨木に触れたい、見たい、そして声を聴きたいという気持ちがムクムクと湧き上がってきた。 もう少し暖かくなったら山に行こう。2020/01/19
030314
2
読んでいるうちに吸い込まれるおもしろさ。読みながら挿絵をみるとなお、分かりが良い。白黒のスケッチが一見、とっつきにくい感じがしたが、ハナシの理解を良く助ける。アーバスキュラー菌根菌と共生関係のイタヤカエデ、ギャップとの関係、などなど、樹木の力強さと不思議さを同時に感ずる。2021/02/24