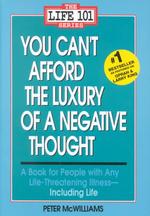内容説明
いつから水道水をあきらめ、ガソリンの2倍もする水を買い求めるようになったのか。安くておいしい水道水ができないのは、水道原水の汚染が原因ではなく、水処理の方法に問題があったからだった。水道水の緩速ろ過技術研究の第一人者が書き下ろした、安く、おいしく、安全、と三拍子そろった「水道水」復活の技術。
目次
1 水道水はなぜまずくなったのか
2 古くて新しい“ゆっくりの生物ろ過処理”
3 生物処理から薬品処理へ
4 水道水が健康に悪いわけ
5 おいしさと安全性は両立しないか
6 浄水処理法の見直しが始まった
7 自分でもつくれる浄水場
8 もっと知りたい人へ
著者等紹介
中本信忠[ナカモトノブタダ]
信州大学繊維学部応用生物科学科教授。数少ない日本の水道水の緩速ろ過技術研究の第一人者。1942年、東京都世田谷区生まれ。東京都立大学理学部生物学科卒、同大学院で微生物生態学、藻類繁殖と栄養塩の関係を研究。1973年、東京都の水道水源ダム湖である下久保ダム湖の流入部が褐色に変色する原因は、鞭毛藻ペリディニウムの大繁殖であることをつきとめ、淡水赤潮現象として日本で始めて報告した。サンパウロ大学、サンカルロス大学で、ブラジル人による陸水学の創成期にダム湖生態系を中心に研究指導。この間、水質を生物の立場で評価するMBOD法という新しい評価法を開発した。この方法は、後にリン規制をするための琵琶湖富栄養化防止条例制定に使われた。創設まもないインドネシア科学院陸水研究センターでも研究指導の機会を得、陸水学の発展にかかわる。生物の立場で水質・水環境を考え、自然界の生物現象を解析。それを応用学部の研究者・教官として人間社会に役立てようとしてきた。1990年より現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
baboocon
annie