出版社内容情報
大学生・研究者から、ODA専門官、世銀エコノミスト、NGOスタッフまで、幅広く参加している日本最大の開発メーリングリストの主催者が、アジア、アフリカ、ラテンアメリカでの林業専門家、住民参加型の村落開発のフィールドワーカーとしての豊富な経験をもとに書き下ろしたスーパーガイド。
開発ワーカーが開発学の理論と実践のハザマで悩みながら、自分を磨くための全65章。
【書評再録】
●国際開発ジャーナル評(2001年2月号)=『国際協力・地域開発メーリングリスト』を主宰する論客による待望の書き下ろし。開発ワーカーが持つべき多くの視座を与えてくれる。多くの学生、現場のワーカーに一読をお勧めしたい。
●JICAフロンティア評(2001年2月号)=開発援助のみならず、日常の場面でも必要な視点が随所に込められている。著者自身が開発に携わって、常に「本当にこれでいいのだろうか」と自問していることがよくわかる、真摯かつ真剣な好著である。
●教育新聞評(2001年4月26日)=様々な「開発」の仕事に携わる人、それを目指す人のためのヒント集。
現場の悩みや開発理論の疑問などを、ていねいに説明し、読者の視点の選択肢を豊にしてくれる。日本国内の公共事業や地域活性化・社会開発のテキストとしてもぴったりだ。
【読者の声】
●男性(53歳)=私も著者同様、JOCX、JICA専門家コンサル業務で10年余、開発途上国と関わってきました。非常に納得ができます。
●男性(29歳)=ページ数は薄いものの中味は濃いので大満足です。実は私も協力隊OBでした。1ページ読み返すたびに冷や汗が出ます。すべての「開発」にたずさわる人に読んでほしい本です。
【内容紹介】本書「はじめに」より
「開発」という言葉の意味もろくすっぽわからない状態からこの世界にかかわるようになって、20年が過ぎてしまった。アジア、アフリカ、ラテンアメリカと世界各地で働く機会があり、いろいろな体験ができたし、見聞もできた。遅ればせながら開発学を学ぶ機会も得て、それまでの自分の無知と無謀さに恥じ入ったこともあった。本書はそうして学んだことを、開発の仕事に携わる、あるいは開発の世界を目指す人たちと分かち合うために書いたものである。また、筆者が主催する、会員数3000人ほどのメーリングリスト(http://dwml.com)上でのやり取りが、本書執筆の上で、おおいに参考になった。フィールド経験のない大学生からJICAの専門家、NGOの草の根ワーカー、世界銀行のエコノミストまで、個人の立場で自由に発言されてきたことが、筆者にとっていくつかの論点を逆照射してくれたのだ。
本書は、開発ワーカー(および、開発、環境に関わる仕事に関心のある読者)のための「ガイド、ヒント集」という内容であるが、実際には本書を読んだからと言ってそのままで良い開発の仕事ができるわけではない。本書は「ハウツー本」でもなければ、「裏技」を示すための書でもない。複雑な要因が絡み合う途上国の社会、その中で働いていく開発の仕事に、唯一の解答や、「これが最も良い」と言い切れる手法などは多分存在しない。必要なのは常に自分を磨き、自分の行為を見つめ直し、人々の話に耳をすませ、常に変化している状況、その時点で何が良いかを考え、そして進んでいくことだろう。
本書で意図するのは解答を示すことではなく、筆者が経験の中で学んだ「ものの見方」を示し、読者の視点の選択肢を、多少なりとも豊かにするのに貢献することである。判断するのは読者一人一人である。この本は副読本になるかもしれないが、教科書ではないことを明記しておきたい。
本書の内容はかなり厳しいことも含んでいるし、人によっては耳が痛いこともあろう。筆者の普段の言動が「厳しすぎる」と人から評されていることもまた事実である。しかし、日本の開発ワーカーは「何かをしてあげる」ために出かける人々である。「良いことをしている」というガードに守られて、日本の人たちから厳しい評価を受けることは少ない。そして、途上国では「ドナー」という立場になって、現地の人たちから厳しい評価を受けることもまたない。それでは自分たちで自分たちに対して厳しい目を向ける以外に、自分たちを正常に保つ手段があるだろうか?そしてそのような危うい存在である開発ワーカーの考えや行いが、途上国の人たちに大きな影響を及ぼすのである。自己批判を欠いた開発ワーカーほど怖いものはないのがおわかりになると思う。開発ワーカーは最も自分に厳しくなくてはいけない存在なのである。
開発の目的は豊かさの実現である。1人の開発ワーカーが、新たな1つの視点を開くことによって、支援の対象となっている人々は、豊かさの実現にさらに1歩近づくことができるかもしれない。そうした願いをもって本書をしたためた。
【主要目次】
▲▲第1章 外部者の視点=リアリティと豊かさ/隠された仮説/学問と開発/援助と開発/緊急援助と開発援助/マクロ経済と地域住民/貧困とジェンダー/地球環境と地域住民/木を見て森を見ず/組織の論理/顔の見える援助
▲▲第2章 開発にかかわる個人として=開発ワーカーの理想はゴルゴ13である/事前の勉強/資料を疑え/調査か開発か/主役は誰か/カリスマはいらない/感覚をとぎすませる/言葉と田んぼ/基本は基本/悪いのは自分/依存心/逃げるが勝ち
▲▲第3章 専門家の落とし穴=視点は複数/手段と目的/誰を啓蒙すべきか/農業システム神話/生産性至上主義/生産と供給/「土地」生産性神話/自作自演/原因と結果/平年並み症候群/競争と棲み分け/隠された被害者
▲▲第4章 人々の視点=貧困とは何か/住民はただでは参加しない/天使はいない/所有の問題/優先順位/住民は知識を持っている/利益とリスク/外部者は資源である/長期的視点/男と女/社会の中の単位/村長は代表していない
▲▲第5章 開発のアプローチ=目的重視とプロセス重視/参加とは何か/学習と行動への参加(PLA)/ツールはツール/楽しいイベントと参加は違う/信頼関係が先/すべてを知らなくてもよい/子ども目線/いないのは誰だ/誰にでもわかるか/同じにはならない/普及するのは住民/トップダウンの参加型/日本らしさは不要
▲▲第6章 プロジェクトというもの=プロジェクトありき/PCMの落とし穴/プロジェクトには参加しない/プロジェクトは持続しなくてよい
内容説明
大学生・研究者から、ODA専門官、世銀エコノミスト、NGOスタッフまで、幅広く参加している日本最大の開発メーリングリストの主催者が、アジア、アフリカ、ラテンアメリカでの林業専門家、住民参加型の村落開発のフィールドワーカーとして、豊富な経験をもとに書き下ろしたスーパーガイド。開発ワーカーが開発学の理論と実践のハザマで悩みながら、自分を磨くための全65章。
目次
第1章 外部者の視点
第2章 開発にかかわる個人として
第3章 専門家の落とし穴
第4章 人々の視点
第5章 開発のアプローチ
第6章 プロジェクトというもの
-
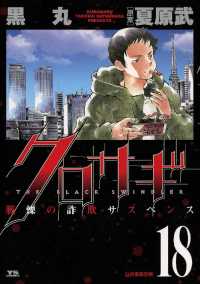
- 電子書籍
- クロサギ(18) ヤングサンデーコミッ…







