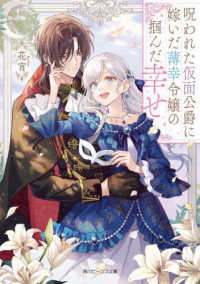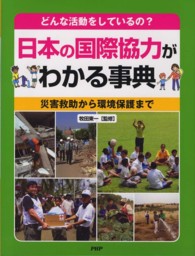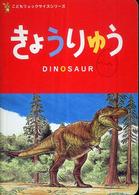出版社内容情報
ヨーロッパの森林や、田園、山村のたたずまいの美しさを造りだしている背景には、文豪ゲーテや詩人シラーなども関わってきた、数世紀におよぶ国土の環境保全に対する国民意識の醸成がある。
200年におよぶヨーロッパの里山保全運動や、アルプスの観光地化と自然・景観保護の歴史、また、ワンダーフォーゲル運動の自然観を解説。
ドイツを中心とする、ヨーロッパの農業、林業、環境行政の文化・思想的背景を初めて明らかにした本書は、日本の森林保全や農山村地域の活性化に不可欠なさまざまな要素を浮き彫りにする。
【書評再録】
●朝日新聞「気になる本」(1999年8月29日)=高級官僚といわれる人が、こういう地味な本を訳していた。幻の魚を見つけたようにうれしい。
●信濃毎日新聞評(1999年9月19日)=個々の狭い専門領域から歴史を描くのではなく、文化全体の視点から歴史をとらえている点が本書の魅力である。21世紀に向けての私たちの生き方や、新しい社会や経済、文化のあり方を考える上で、豊富な材料を提供し、大きな示唆を与えてくれる。自然保護に関心がある人だけでなく、広範の方に一読をお薦めしたい本である。
●林業技術評(1999年9月号)=森林や環境保護に関心を持つ人に本書を読んでいただき、森林や景観保護にかかわる文化、思想の奥深さに触れてもらいたいと思います。
●林業経済評(1999年9月号)=森林文化に関心を持ち、この分野で未知の課題を究めていこうとする者にとって、これこそ必読の書といえるであろう。まさに待望の書であったという思いが強くするのである。
【読者の声】
■男性(48歳)森林管理署勤務=たいへん内容がくわしく、とても参考になりました。
■男性(54歳)=それぞれの国や地域における自然と人間とのかかわり方の違い、また、思想や歴史観による自然の中での人間の位置付け等、たいへん参考になった。
【内容紹介】本書「訳者まえがき」より
20世紀の社会や経済、文化を支配した内外の大きな枠組みが世紀末にいたって音を立てて崩壊している。そしてまた、差し迫った問題としてバブル経済とその崩壊でさまざまな面でいたんだ日本をいかに立て直すべきかが問われている。そうしたなかで、この国のかたちがどうあるべきかという議論がこのごろ盛んに行われている。
まさにその意味では国の基本である自然、生存の基盤であり文化の母胎である自然、森とわたしたち一人ひとりの関係がどうあるべきかという問題や、自然をどう守り育むかという問題を、いままさに、これまでの小手先やうわべの話としてではなく、一人ひとりが真剣に考えるべきときなのではないだろうか。自然と人間との関係の再構築がせまられている現在、自然観、森林観や環境倫理にまでさかのぼって、この問題がさまざまな角度から議論され、真の国民意識の形成が図られ、具体的な行動に移されるべきではないだろうか。
ドイツとその周辺諸国の森をはじめとする自然や風景の保護運動あるいは環境保護思想史を描いたこの本を訳して、日本の読者に提供しようと、切実に思うにいたったのは、まさにこの点にある。
環境大国といわれるドイツやその周りの国々とわが国では、エコロジーに関する国や国民の意識や具体的対応がいささか様相を異にしているのに気づく。ヨーロッパの森や自然の豊かさ、田園や山村のたたずまいの美しさを支えているのは、数世紀におよんで醸成されてきた森や自然環境・国土保全に対する高い国民意識であり、これを背景とした国や地方の政策やNGOなどの活動であるように思われる。
ドイツやスイスをはじめとするヨーロッパでの自然観の形成や自然環境・風景・国土保全運動や、その思想の成立過程は、これまで日本では紹介されることが少なかった。そこには、文学や哲学、社会思想が推力となった確固とした思潮が流れている。それらを浮き彫りにした本書は、自然と人間との関係の再構築のみならず、21世紀に向けてのわたしたちの生き方や、新しい社会や経済や文化のあり方についての議論に欠くことのできない豊富な材料を提供し、大きな示唆を与えてくれるのである。
【内容紹介】本書「はじめに」より抜粋
本書の各章は、古本を寄せ集めたようなものとは性格を異にする。各章は過去のエコロジーの諸問題を論じているが、同時に、この250年間に加速し続けてきた都市化や工業化を背景とする現代のエコロジーの諸問題を示唆しているのである。
自然をたんに人間のための「環境」として見るような人間中心的な態度は、これからは改めなければならない。それゆえ、たんなる環境保護だけに力を尽くすのは、積極的なこととはいえない。人間のための有用性の観点だけから自然を見るのではなく、動物であろうと植物であろうと生きとし生けるものを純粋に人間がいのちあるものとして尊厳の念をもって見るという態度こそ高い価値を持つ。すなわち新しい倫理にもとづくものといえるのである。きわめて重要なことは兄弟姉妹に対するような心で人間が自分を地上のいきもののひとつと感じることであり、ほかのものを食いものとするような心、破壊するような心で、自分とほかのすべてのものとを遮断しないことである。
【主要目次】
▲▲第1章・まずは木々だ、わたしたちはそれからだ!-----森の保護のさまざまな動き
▲▲第2章・エコロジカルな楽園と実利本位の植栽地-----啓蒙時代の教育家たちのたどった道
▲第1節・近代化、そして自然への憧れ
▲第2節・感傷的「天才たち」と「理性的」啓蒙主義者の争い
▲第3節・「若きヴェルテルの悩み」---先鋭化する対立
▲第4節・自然のなかの教育農場の構想とその挫折
▲第5節・農民の敵であった君主の森
▲第6節・実利重視に傾く汎愛学舎、感傷を失う農業や林業
▲第7節・エコロジカルで牧歌的な楽園との決別
▲第8節・憧れの楽園となりえなかったアメリカ
▲▲第3章・ヨーロッパの庭から競技場に変わったアルプス
▲第1節・もてあそばれた秀峰ギリ
▲第2節・実利的に利用されたアルプス(伝統的農林業と農民的自然観/近代化するアルプスの経済とその影響/登山や保養---健康づくりとアルプス)
▲第3節・自然の美や崇高さに感激したルソーやゲーテ(美を求めて/崇高さを感ずるひとびと)
▲第4節・科学や技術などによるアルプスの征服(道路や鉄道により進む開発/ツーリズムの隆盛/征服される山々の頂き)
▲第5節・文学や絵画や庭園によるアルプスの表現(スイスを旅した多くの文人/絵画に描かれた壮大なパノラマ/大衆美術に描かれたアルプス/庭園に模倣されたスイスの風景)
▲第6節・道徳を再生させ、精神をよみがえらせるアルプス
▲第7節・地霊のはびこる山、神に通じたアルプス
▲第8節・保護の試みはどのようにしてはじまったのか(峠に巡礼用の宿坊を設けた時代---人間をアルプスから保護する動き/ツーリズムによる山岳住民のモラルの退廃と、古きよき山での暮らしぶりの保護/良質なツーリズムを求めて---持ち込まれた大都会のホテル・風俗への批判/美観を損なうマッターホルン鉄道計画に反対した郷土保護運動/高山植物を守り、山地を保全する---エコロジーに根ざした自然保護の曙)
▲第9節・真の利他的な自然保護の実現を
▲▲第4章・森にレクリエーションを求めた勤労者たち-----労働者は自然破壊の共犯者であったのか
▲第1節・左翼は盲目的に進歩を信仰していたのか
▲第2節・水の汚濁や大気汚染への異議申し立て
▲第3節・自由な森から閉めだされた貧しい農民
▲第4節・ユートピアの森とレクリエーション機能
▲第5節・森の破壊は川を涸らす
▲第6節・自然保護に進歩の展望はあるのか
▲▲第5章・郷土保護連盟-----美を愛でる心とエコロジーの統合
▲第1節・風景はその美しさのゆえに守られなければならない
▲第2節・美の価値を重んじた改良の伝統
▲第3節・悲鳴を上げる風景
▲第4節・美とエコロジーをつなぐ薮や混交林
▲第5節・風景も自然美もまた公共の宝物
▲第6節・郷土保護運動に学ぶ知恵
▲▲第6章・農山村の風景美を好んだ市民層の青年たち-----ワンダーフォーゲルの自然観とその限界
▲▲第7章・エコロジーの宣言「人間と地球」-----進歩に背を向けたひとクラーゲス
▲第1節・非合理主義の哲学者の思想の光と影
▲第2節・原因は「いのち」に敵対する「精神」にあり
▲第3節・今日のエコロジカルな危機を予見した「人間と地球」
▲第4節・クラーゲスの功績と限界
▲▲第8章・楽園を夢みて-----ハンス・パーシェの世界自然保護構想
▲第1節・パーシェの活躍した時代
▲第2節・パーシェの生涯
▲第3節・小説「ルカンガ・ムカラ」
▲第4節・世界自然保護構想の夢と希望
内容説明
ヨーロッパの森林や、田園、山村のたたずまいの美しさを作り出している背景には、文豪ゲーテや詩人シラーなどもかかわってきた、数世紀におよぶ国土の環境保全に対する国民意識の醸成がある。200年におよぶヨーロッパの里山保全運動やアルプスの観光地化と自然・景観の保護の歴史、また、ワンダーフォーゲル運動の自然観を解説。ドイツを中心とする、ヨーロッパの農業、林業、環境行政の文化・思想史的背景を明らかにする。
目次
第1章 「まずは木々だ、わたしたちはそれからだ!」―森の保護のさまざまな動き
第2章 エコロジカルな楽園と実利本位の植栽地―啓蒙時代の教育家たちのたどった道
第3章 ヨーロッパの庭から競技場に変わったアルプス
第4章 森にレクリエーションを求めた勤労者たち―労働者は自然破壊の共犯者であったのか
第5章 郷土保護連盟―美を愛でる心とエコロジーの統合
第6章 農山村の風景美を好んだ市民層の青年たち―ワンダーフォーゲルの自然観とその限界
第7章 エコロジーの宣言「人間と地球」―進歩に背を向けたひとクラーゲス
第8章 楽園を夢みて―ハンス・パーシェの世界自然保護構想