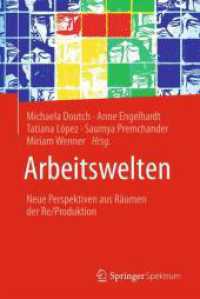こちらの商品には新版があります。
内容説明
インフレ目標とは、中央銀行の独立性とは、デフレの害悪とは。金融政策の世界的権威、アベノミクスに結論を下す。
目次
1 インフレ率の低下が好ましくない理由
2 デフレーション―「あれ」をここで起こさないために
3 インフレ目標を考える一つの視座
4 中央銀行の独立性とは何か?
5 金融政策の長期的な目標と戦略
6 アメリカ経済は今後どうなるか?
7 日本の金融政策、私はこう考える
著者等紹介
高橋洋一[タカハシヨウイチ]
株式会社政策工房代表取締役会長、嘉悦大学教授。1955年、東京都生まれ。東京大学理学部数学科・経済学部経済学科卒業。博士(政策研究)。1980年、大蔵省(現・財務省)入省。プリンストン大学客員研究員時代、のちに連邦準備制度理事会(FRB)議長となるベン・バーナンキ教授の薫陶を受ける。内閣府参事(経済財政諮問会議特命室)、総務大臣補佐官、内閣参事官(総理補佐官補)などを歴任。2007年に財務省が隠す国民の富「霞が関埋蔵金」を公表し、一躍、脚光を浴びる。2008年、退官。現在、大学で教鞭をとるほか、国・地方自治体、政党など政策関係者向けの政策コンサルティングを手がける政策工房を運営している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kolon
3
バーナキンの講演をテキスト化した本。 約20年前の講演だが現在にも色褪せず適用できる内容だ。 バーナキンはノーベル経済学賞受賞者だが、私にも理解出来るマクロ経済論でありリフレ論だ。 バーナキンの講演内容を理解出来ない日本の日銀関係者や財務省官僚がいるとすれば、驚くべきことであるが、どうやら日本の金融当局の多くには理解出来ない人たちが多いらしいし、日本の経済学者も同様だ。 バーナキンの主張はフィリップス曲線で現されるNAIRUを目指すのが中央銀行の使命だ、に尽きるのだが、日銀にも同様に行動して欲しい。 2023/11/13
ほなみ
2
ノーベル経済学賞受賞ということで手に取ってみた。 基本的な経済学の知識が求められて少々苦しかった(経済学部だったのに知識がない。、、) 内容としてはインフレ目標を立て、市場とコミュニケーションを取ることが大事だと。 アベノミクス推奨派ということも非常に納得。 日本のデフレは政治的な問題だという主張は確かにな〜と。リスクを取らない感じはする 2022/10/14
patora22
1
サッカーやラグビーの代表監督を外国から招聘するように、バーナンキ氏が日銀総裁になってくれたらと思ってしまった。 今の首相では無理かな・・2023/01/19
maou
1
米国中央銀行議長であるバーナンキの数々の講演を収録。 間接的にそれらがアベノミクス第一の矢である、「大胆な金融緩和」を肯定している。中央銀行の独立性についても、明確に「目的は政府が設定し、独立しているのは手段である」と述べられており、上念司さんらの著書であった主張が、世界的なスタンダードである事が確認できた。 未だに書店などでもリフレ政策の足を引っ張る国家破綻本などが幅を利かせているが、世界の先進国で「当たり前」の政策を日本でも早く当たり前にし、その先の議論をしないといけないんだなー、と感じた。2013/07/23
Emma
0
確かに経済の知識がなくてもわかるがまだまだ理解が浅いと感じた。経済を勉強して再読したい。バーナンキの政策に対する考え方。物価安定を目指すだけでなく両立可能な雇用の最大化を考えていくべきである。あとは日本で行うべき政策の提案など。少し中身が古いが学ぶことは多くある。2015/01/03