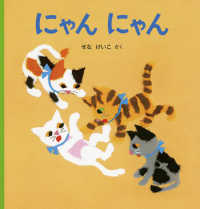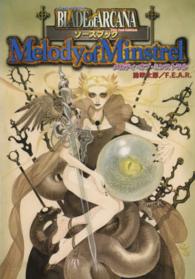内容説明
大人として恥ずかしくない手紙の書き方、相手の心証をよくする電話の応対、センスのある敬語の使い方、ユーモアやあいまいな言葉の効用など、“ことばの教養”が磨かれる珠玉のエッセイ。日常生活に生かしていけば、あなたの絶対語感(ことばの習性)が変わる。
目次
第1章 大人の気づかいは「ことば」にあらわれる
第2章 大人の話し方のできる人・できない人
第3章 大人が使うあいまいな日本語
第4章 得することば・損することば
第5章 敬語はむずかしい
第6章 漢字のこころ・カタカナのセンス
第7章 ことばづかいは「履歴書」
著者等紹介
外山滋比古[トヤマシゲヒコ]
1923年、愛知県生まれ。文学博士。東京文理科大学英文科卒業。雑誌『英語青年』編集長、東京教育大学助教授、お茶の水女子大学教授、昭和女子大学教授を経て、お茶の水女子大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
33
書名や帯のとおりのマニュアル本かと言えば、さに非ず。古老に叱られ叱られ自分の日本語感を正されている感じがして、時に「そんな古臭いことを言われても……」と思いながら読了。H26年度最初の読了本がこれというのも何かの縁だろう。章としては『間のない間抜けな話し方』が、行としては『ことばの乱れは精神の荒廃の指標であるのは、日本語において、ほかの国よりいちじるしいように思われる。』が印象的。2014/04/01
らじこ
30
頭の固いおじさんの説教と世間への反論といったところだろうか。思考の整理学が面白かったので読んでみたのだけれど。読みやすくはあるものの、反骨精神に満ちている。ただ著者の言うこともわからないではない。わたしも、婉曲な言い回しができる日本人ひいては日本語というものが、情緒に富み、美しいとは思う。昔から営まれてきた手紙の礼節もしかり。日本人とは、礼と言葉に対してなんて丁寧な文化を持っているのだろうとも思う。手紙の書き方はわたしも忘れてしまったから、身に染みる思いだったけれど。少し著者の考えが強すぎるように感じた。2015/12/28
にせものばかり
10
個人的には、外山さんの著作ではこの作品が一番役に立ちました。言葉はやはり大切ですね・・。2014/03/22
かつお
5
外山が日本語について思うことを書いてあった。言葉から人柄がわかるものだということを学んだ。2016/06/11
はははるてぃ
5
社社会人として学びたいと思って、読み始めしたがちょっと違っていたかも。でも、意外な事がわかったりでよかった。時代は流れて、文化や習慣も徐々に変化する。日本人特有の長所は後世に残していけるといいのだけど。2013/10/12