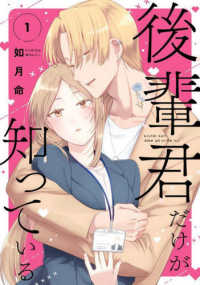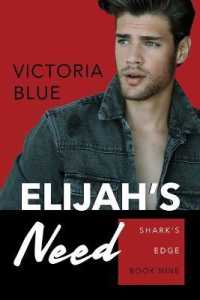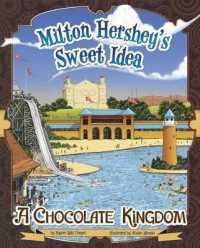内容説明
社会福祉学の基本的な性格として、実践性が研究や教育において強調されているが、いまだに学問的にそのことが実証されているとは言えない現状がある。そのため、単なる実践を紹介するのではなく、実践学になるための基礎づけの研究が必要とされている。社会福祉実習、現場の実践を個人の体験にとどめるのでなく、体験からの学びを学問にしていく取り組みの必要性を痛感している。また、こうした試みは社会福祉学の研究にとどまらず、その教育においても大いに役立つものと考えられる。本書は、上述の課題へ取り組んでいくことを目指している。最初に社会福祉援助技術の方法論的検討から、臨床福祉学のアプローチを提示し、続いて、従来の学問が「臨床への学」であったことを検証し、実践や体験を大切にするという視点から「臨床からの学」として社会福祉実習学の試みを行っている。さらに、臨床福祉学の真骨頂を表すものとして、今日の対人援助サービスにおける実践的な課題へ取り組んでいる。
目次
第1部 臨床福祉学のアプローチ―社会福祉援助技術への方法論的問い(対人援助の方法論的基礎づけ;つながりの文化における対人援助の可能性―日本人の人間関係と社会福祉援助技術;社会福祉援助技術における生活への視点―生活の連続性を支える基礎的地平の理解)
第2部 社会福祉実習学の試み―「臨床からの学」としての実習と実践教育(「臨床からの学」としての社会福祉実習学;臨床的視点からの社会福祉実習教育の展開―体験からの学びの概念化;卒後教育の課題と社会福祉実習教育)
第3部 臨床福祉学の実践―「臨床からの学」から見えてくる実践の課題(苦情対応に表れる組織の姿と専門職の態度―社会から評価される保健医療・福祉サービス;聴く専門性としてのインフォームド・コンセント;家族への自立―厄介、“だから”かけがえのないものとのかかわり)
著者等紹介
佐藤俊一[サトウシュンイチ]
1952年静岡県三ケ日町に生まれる。1977年立教大学大学院社会学研究科修士課程修了(応用社会学専攻)。1977~1992年社会福祉法人白十字会東京白十字病院医事課長などとして勤務。1992年鹿児島経済大学社会学部社会福祉学科助教授。1997年淑徳大学社会学部社会福祉学科助教授。1998年淑徳大学社会学部社会福祉学科教授。現在に至る
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。