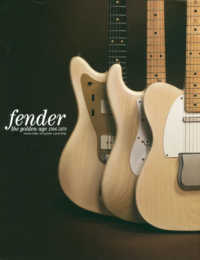内容説明
本書は、アメリカのサービス評価に関する専門書「長期ケアの満足度評価法―利用者の声をよく聴くための実用的アプローチ」の日本語訳である。専門書とはいっても、これは研究者のために書かれた学術書ではない。むしろ、そのタイトルが示すように、ヘルスケアや介護サービスの評価に関心のある専門職が現場で参考書として使えるものである。
目次
評価活動が根づいている社会、アメリカ
第1部 サービス利用者の満足度を調査するにあたって―背景と方法(サービス利用者満足度を考察するために;サービス利用者満足度に関する理論;サービス利用者満足度の測定方法;サービス利用者のデータ収集法の実施)
第2部 サービス利用者満足度の測定の種類とアプローチ―ケアの現場と方法(在宅ケア利用者の満足度の測定;ナーシングホームとアシスティッドリビング入所者の満足度;ヘルスケアの利用者満足度の測定;サービス利用者の調査結果を用いて:サービス向上サイクルの完成)
アメリカでサービス利用者満足度に対する関心が高まってきた背景
著者等紹介
アプルバウム,ロバート[アプルバウム,ロバート][Applebaum,Robert A.]
マイアミ大学(オハイオ州)教授、スクリプス・ジェロントロジー・センター副所長
多々良紀夫[タタラトシオ]
哲学博士。1937年静岡県生まれ。1960年関西学院大学文学部卒。1969年ワシントン大学社会事業学大学院修士号。1975年ブリン・マーカレッジ社会事業・社会調査学大学院博士号。ブリン・マーカレッジ大学院講師(1972~1976年)を経て、米国公的福祉協会研究調査部長(1977~1998年)を務める。その間、米国高齢者虐待問題研究所(National Center on Elder Abuse―NCEA)所長(1988~1998年)、国際社会福祉協議会米国委員会副会長(1988~1992年)および会長(1992~1997年)等を歴任。また、連邦政府、いくつかの州政府や研究機関のアドバイザーを務める。連邦議会の高齢者問題を担当する委員会の公聴会では、高齢者虐待予防や治療に関する政策提言を数回にわたって行う。さらに、50近い福祉分野の研究・評価・訓練プロジェクトの主任研究者を務め、全国レベルで活動を指揮する一方、研究者の養成にあたる。1998年4月より、淑徳大学社会学部教授となる
塚田典子[ツカダノリコ]
哲学博士。1959年広島県生まれ。1985年福岡教育大学大学院修士号(教育学)。1993年米国オハイオ州立マイアミ大学大学院修士号(老年学)。1997年米国カリフォルニア州カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院公共政策・社会調査学部博士号(社会福祉学・老年学専攻)。福岡教育大学附属久留米中学校文部教官教諭(1985~1990年)を経て、アメリカへ留学。National Institute on Aging(国立老年研究所)でインターンシップ(1992年および1993年)。博士号修得後、UCLA Center for Policy Research and Aging(1998年)およびCharles R.Drew University of Medicine and Science(1998年)で非常勤研究員を務めた。その後、UCLA非常勤講師(1999年)を経て、日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科助手(1999年5月)。2001年4月より同研究科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。