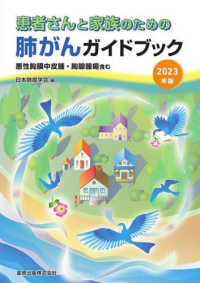内容説明
ドイツやフランスでは法律用語の多くは小学生でも知って理解している。欧州の法律用語は日常語で、日本の法律用語はなぜよそゆきなのか。法律用語の背後に深く根ざす欧州的な人間観を透徹しながら、用語の意味を吟味する。
目次
「法」と「権利」
「契約」
「人」
「意思表示」
「法律行為」
「債務」と「責任」
「担保」
「物」
「所有」と「占有」
「組合」と「会社」
「公序良俗」
「不法行為」
著者等紹介
古田裕清[フルタヒロキヨ]
1963年生まれ。ミュンヘン大学哲学博士(Dr.phil.)。現在、中央大学法学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
_apojun_
5
図書館本。 職種が変わって、これまで全く縁のなかった法律系の資格勉強を始めたとき、あまりにも独特な法律用語に面喰いました。 なぜこんな言葉使いをしているのか謎だったので、それが少しでも解決するかと思って手に取ってみました。 想像していた内容とは少し違って、日本の法律のベースとなったドイツやフランスで使われている用語と対比することによって、その裏にある国民性とか文化とか歴史を認識できるという感じです。 というわけで、いまだに「善意の第三者には対抗できない」にはピンときません。2024/04/21
Hisashi Tokunaga
0
メモ再読;なるほどとメモったのは①日本で公は公家、中国古代では大師・大律・大保を三公。独で公̈Offentlich=Offen=Open(英)透明という意味も含む。②仏では1994年生命倫理立法で民法配列「人」「物」の間に「人体」を入れ人体を目的とする売買は無効とし、人体に対する不法な扱いには差止請求できることとした。2019/01/17
-

- 電子書籍
- 魔王アプリでS級ハンターになれました【…
-
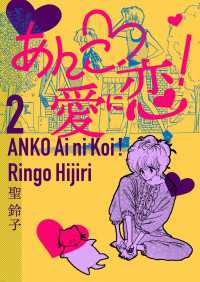
- 電子書籍
- あんこ・愛に恋! 2巻