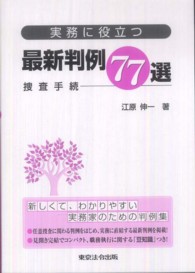内容説明
19世ドイツの建築家ゼムパー(1803‐79)の思想には、建築を部分的に変化させるのではなく、現象として見える像の全体を変えてしまうほどの力がある。この場合、「現象として見える像の全体」とは様式に他ならず、それは新様式創生論とも言えるであろう。本書はその様式の本質と、わが国を初め現代建築への多大な影響を論じる。
目次
ゼムパー建築論の前史
『覚書』に描かれる表面の美、ポリクロミー
一八三〇年前後、歴史主義の現れ―芸術と装飾の復興
始原への探究
建築の四要素
科学・産業・芸術
様式と被覆―ロンドン講義第一回を中心に
装飾と被覆
ウィーンの十九世紀建築と歴史主義
オットー・ヴァーグナーの「近代建築」と被覆
被覆/サーフェス―アドルフ・ロースから現在まで
著者等紹介
川向正人[カワムカイマサト]
1950年香川県生まれ。1974年東京大学建築学科卒業、同大学院進学。1977‐79年政府給費生としてウィーン大学美術史研究所留学。明治大学助手・東北工業大学助教授を経て、1993年東京理科大学助教授、2002年同教授、2005年より東京理科大学・小布施町まちづくり研究所長兼務。2016年定年、東京理科大学名誉教授。主たる受賞:2016年日本建築学会賞(業績)、同学会教育賞(教育貢献)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
inoue
0
ゼムパーの被覆論の形成に至る、ポリクロミー論等の19世紀前半の建築界の動向や、自身の始原への探求、建築の四要素、囲いの重視、工芸への視野の拡大等が丁寧に書かれる。様式が理念と地域、経済、施主等々の諸条件との関係によって表出するという図式は、近代以降につながるものであり、その為に歴史を参照する態度は19世紀的合理主義の知を感じる。 後半はヴァーグナー、ロースや現代までの影響が記述され、隈研吾が様々なマテリアル・技法を用いて被覆を試み、知見を集積する態度とゼムパーが歴史を参照する態度を重ねていることは面白い。2025/08/30
キャラ
0
被覆論により、建築とは従来のvolume,装飾の捉え方ではなく、結構性、つまり構造や技術の織物とみなす考え方。結構をY=C(x×y...)の係数で表すことで、そこに人間生活の表象、コンテクストの編み込まれ方をみることができ(芸術形態の段階?)、これまでの様式論を覆す内容。surfaceや境界についての理論によって、形の比例関係やオーダーから見る建築の本質や美は乗り越えられたとし、表象についての言説は変わっただろうが、全体の構成へと及ぶ、空間理論のようなラディカルな展開になったかどうかは正直わからない。2025/04/28
-

- 電子書籍
- 岐阜県のお城・館一覧
-

- 電子書籍
- 花魁どぉる~新宿遊廓恋物語~【フルカラ…


![ポリドロンチャレンジセット [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44877/4487773326.jpg)