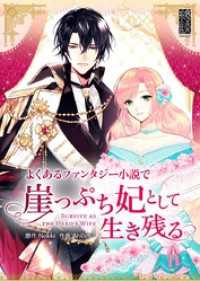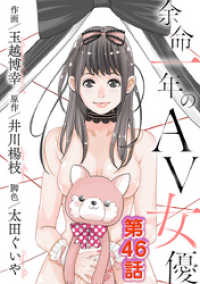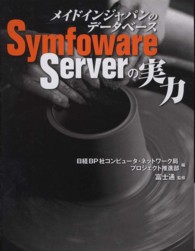内容説明
子どもの自立のために「やってはいけないこと」&「やるべきこと」GoogleやAmazonも注目!「社会情動的スキル」を子どもに身につけさせる方法とは?全国学力・学習状況調査、ハーバード大学、OECD(経済協力開発機構)…etc世界中の研究が明らかにした子育ての新常識。
目次
1 非認知能力が注目される理由(世界で認められる非認知能力の重要性)
2 自立した大人に育てるために親がやってはいけないこと(最先端の研究でわかった子育ての新常識;子どもの自立をさまたげる親の×行動;子どものこまった言動 こんなときどうする!?)
3 非認知能力も認知能力も両方伸ばすために親がやるべきこと(認知能力と非認知能力;「目標を達成する力」を伸ばす方法;「他者と協働する力」を伸ばす方法 ほか)
著者等紹介
浜野隆[ハマノタカシ]
お茶の水女子大学基幹研究院教授。専門は教育社会学・教育開発論。研究内容は「子育てと非認知能力」「家庭環境と学力」「教育格差」「保育・幼児教育」など多岐にわたる。文部科学省委託の「学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究」の代表者として家庭環境と学力・非認知的能力の関係を分析。「全国学力・学習状況調査」個票データ貸与に関する有識者会議委員、世田谷区教育委員会教育研究アドバイザーとして教育行政にも関わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいきち
35
子どもに対して、年長者の立場から頭ごなしに叱る、教える…という教育はもう古いのですね。親が模範になる必要も無さそう。子どもの目線に立って考えて、一緒に楽しみながら学ぶ。親も子どもと一緒に成長する。この「共有型しつけ」が科学的にも子どもにとってとても良い影響を及ぼすのだと。子育てへのハードルがぐっと下がったような気がしました。親も楽しみながら子育てをすることが大切だと分かりました。2024/10/26
U-Tchallenge
1
よいと言われる子育てについて網羅的に紹介されている内容となっている。一つひとつの項目ごとに参考・引用文献が示されており、とても丁寧で誠実なつくりとなっている。しかし、硬いわけではなくすらすらと読みやすいように思った。我が子を育てるだけでなく、広く子どもを育てている者にとってはとても有益な一冊である。気になった項目をさらに深く学びたい、と思わされた。2023/11/07
あに
0
児童館で子の様子を見ながら何ヶ月もかけて読んだので内容が頭に入っていない。けど、認知能力から非認知能力が重要視されているというのは他の育児書にも書いてあった。読み書きや計算など、小さい頃から早めにやらせて目に見える能力を先んじてと思いがちだけど、言われてみれば高校時代遊び倒していた子が受験にシフトしてから急激に伸びたなんてことがあったよな。あれも非認知能力、粘り強さや集中力だったのかな。子どもができてから認知能力取得を早めにと思っていたけど学力が幸せに直結するわけでもないしなと冷静になれた。2024/09/03
松村 英治
0
根拠となる論文が明確な、貴重な子育て本。2023/09/11