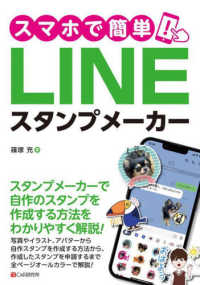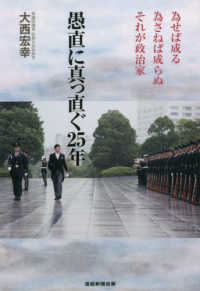出版社内容情報
都道府県の境である「県境」。
そこはただの境目ではなく、“なぜそこが境目となったのか”というさまざまな理由が存在します。
本書は、著者が現地を取材したからこそわかったその理由を紹介します。また全スポットに地図を掲載しているので、県境の場所がひとめで分かります。写真もあわせて掲載しているので、実際に県境を旅しているような気分になれます。
47都道府県すべてのスポットを紹介しており、日本全国どの地域にお住まいの方でも身近に感じられてお楽しみいただくことができます。
目次
県境番号とは?
第1章 北海道・東北
第2章 関東
第3章 中部
第4章 近畿
第5章 中国・四国
第6章 九州
著者等紹介
西村まさゆき[ニシムラマサユキ]
1975年鳥取県生まれ。高校卒業後上京。編集プロダクションに10年勤務。2010年よりフリーライター。Webメディア『デイリーポータルZ』レギュラー連載中。とくに歴史、地理、地図など社会科に関する記事が多い。その他『国語辞典ナイト』『路線図ナイト』などのイベントも行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shinjuro Ogino
1
遠い地の話が続くが、少し紹介。例えばa)幕末まで徳島藩の藩領であった淡路島が兵庫県なのは、代々淡路島を支配していた徳島藩の家老と徳島藩との内紛に、新政府が両成敗をし、結果淡路島が兵庫県に編入された。b)JR備前福河駅が兵庫県の理由は、福河地区がかつて兵庫県明石地区と経済関係が強く、廃藩置県に当り住民の兵庫県帰属運動がおこったのに対応したもの。しかし漁業権関係で岡山県の抵抗があって海の県境は岡山県側に大きく食い込んだ。手許の地図帳で確認。c)県境番号29の千葉神奈川県境の長さが0㎞というのは意味不明。2025/04/16