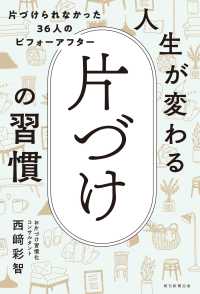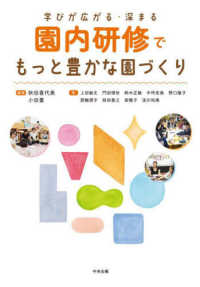内容説明
秀吉が天下統一を目指すなか、16歳で即位。聚楽第行幸、朝鮮出兵、関ヶ原合戦と近世の政治体制の大きな転換点に若き天皇として叡慮を示す一方、名筆・画才の誉れ高く学問を奨励。神武以来の朝儀復興、文化史上不朽の業績である勅版刊行など近世日本の文芸復興に大きく貢献した業績を検証する。
目次
序章 総論(後陽成天皇とその時代)
第1章 後陽成天皇と近世統一政権(豊臣政権と朝廷;豊臣摂関家の形成と「武家家格制」;誠仁親王と勧修寺晴子;正親町上皇と『院中御湯殿上日話』;太閤秀吉の「唐入り」構想と朝廷;関白豊臣秀次と文事策;江戸幕府の成立と朝廷)
第2章 後陽成天皇時代の社会と文化(内裏・院御所の造営と公家屋敷地の形成;皇位継承儀礼と後陽成天皇―立太子儀再興計画の中止とその影響;近世初期の出版と慶長勅版;後陽成天皇と桃山時代の美術工芸;後陽成天皇の書)
第3章 後陽成天皇の文芸復興(後陽成天皇時代の漢詩文―英甫永雄を例に;後陽成天皇と和漢聯句;後陽成天皇と和歌―近世初期宮廷歌壇の「みやび」;後陽成天皇時代の連歌;後陽成天皇と歌学)
付録
後陽成天皇関連史料
著者等紹介
橋本政宣[ハシモトマサノブ]
1943年、福井県生まれ。國學院大学文学研究科日本史学専攻博士課程中退。博士(歴史学)。東京大学史料編纂所教授を経て、東京大学名誉教授。舟津神社宮司。主な著書に『近世公家社会の研究』(吉川弘文館、2002年、第一回徳川賞受賞)などがある
山口和夫[ヤマグチカズオ]
1963年、東京都生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程中退。博士(史学)。現在、東京大学史料編纂所教授
矢部健太郎[ヤベケンタロウ]
1972年、東京都生まれ。國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程修了、博士(歴史学)。防衛大学校人文社会科学群専任講師を経て、國學院大學文学部教授・文学部長
久保貴子[クボタカコ]
1960年、岡山県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科史学専攻後期課程満期退学。博士(文学・早稲田大学)。現在、早稲田大学・昭和女子大学非常勤講師
遠藤珠紀[エンドウタマキ]
1977年、愛知県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学。博士(文学)。東京大学史料編纂所准教授。中世朝廷制度の研究を専門とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 絶世の武魂【タテヨミ】第56話 pic…