出版社内容情報
《江戸時代版・住みたい街ランキング?》
身分別に居住地を厳密に定められていた江戸時代、庶民に与えられた土地は江戸市中のわずか15%しかなく、その大半が環境劣悪な低湿地だった。狭い長屋は日当たりが悪く湿気が充満している。大雨が降れば道は川のようになって家の中まで水浸し、燃えやすい木造住宅が密集する街は常に大火事の危険もあった。
不快なだけではなく危険な場所なのだが、当時は大半の人々がそれで満足していたようである。勝手に居住地を選ぶことのできない時代、そういったことに不満を抱くような思考が欠落していたのかもしれない。
たとえ居住地域を厳しく制限された状況でも、人々は選択可能な範囲内で、自分にとって最も居心地の良い場所を探して住んでいたと考えると……江戸時代に住みたい街ランキングなんていうものがあれば、どんな結果になっていただろうか?
さらに居住地が自由に選べるようになった維新後、郊外の住宅地開発がさかんになった関東大震災後、団地が林立するニュータウンが次々に造成された高度経済成長期、そして、都心部の駅前に超高層タワーマンションが建つようになった現代と……東京は激しく変化しつづけている。
100年前まで、いや、それよりもさらに昔の江戸時代にまで遡って、それぞれの時代に生きた人々の「住みたい街」を調べてみようと思う。
【目次】
内容説明
Q.江戸のお殿様が住みたい街第1位は…??芸術家は田端に住みがち?次の王者はあの駅だった?住みたい街は将来なくなる?江戸城からタワマンまで…「住みたい街」をキーワードに“東京”の歴史を解剖する。
目次
第1章 「住みたい街」の創世記(江戸は住むには狭すぎる!;徳川家康のウォーターフロント開発 ほか)
第2章 震災の恐怖から「住みたい街」は生まれた(東は工場地 西は住宅地;“西側”は軍用地として発展していった ほか)
第3章 戦後のマイホーム信仰と「住みたい街」(大量のホームレスを発生させた日本史上最悪の住宅難;空き家が見つかれば奇跡 ほか)
第4章 バブル景気で東京は拡大していく(バブル景気で地価は急上昇;都心は“住めない街”と化してゆく ほか)
第5章 震災と感染症で「住みたい街」が変わる(震災ショックで人気エリアにも変化が;タワマンカーストの崩壊 ほか)
著者等紹介
青山誠[アオヤママコト]
大阪芸術大学卒業。web「さんたつ」で「街の歌が聴こえる」を連載中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
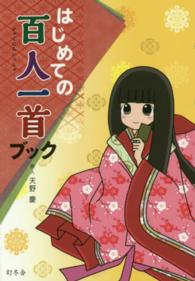
- 和書
- はじめての百人一首ブック






