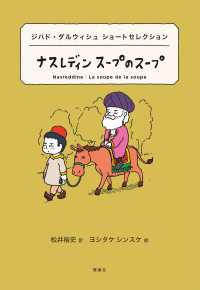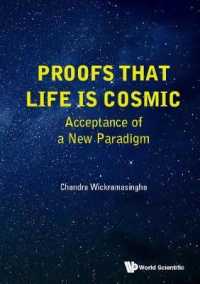出版社内容情報
十進法に基づく円形新貨幣を鋳造し、新しい通貨制度を確立。地租改正や廃藩置県を行い、租税の基盤を築く。全国に鉄道網や大工場を築くなど、国を挙げて殖産興業に取り組み、世界市場で存在感を発揮する――。
明治維新は、わずか数年で国家の近代化を実現した、日本史上の〝奇跡〟と呼べるような出来事だった。
司馬遼太郎の『歳月』によると、幕末~明治初年の国家歳入は1100万石だったという。1100万石というと、現在の価値にすると5500億円程度とされる。その少ない元手の中で、明治新政府はいかにして、革新的なイノベーションを起こしたのか。数々の革命を実現するための資金はどう調達していたのか。そしてその結果、日本人は何を得て、何を失ったのか…。お金の動きから見る、新しい幕末~明治維新史。
内容説明
日本史最大の革命の費用はどのようにして捻出されたのか?国家体制、殖産興業、教育、軍事…、明治維新の真実を金銭面から分析。
目次
第1章 戊辰戦争の負債(討幕しようにも金がなかった新政府;金欠が生んだ悲劇「偽官軍事件」 ほか)
第2章 「近代化」は激痛がともなう改革(藩札の乱発も見て見ぬふり;財政難は武士の忠誠心をも失わせる ほか)
第3章 「文明国」に進化するためのコスト(世界経済に疎かったことが招いた金の大量流出;治外法権で悪徳商人が跋扈 ほか)
第4章 最良の兵士と労働者を育んだ教育制度(殖産興業で国を富ませ、兵を強くする;民間の製糸工場の過酷な現状 ほか)
第5章 政府が強くなれば国民の負担は増す!?(征韓論争に見える新政府の本音;西南戦争で手に入れた“打出の小槌”が日本を不幸にする ほか)
著者等紹介
青山誠[アオヤママコト]
大阪芸術大学卒業。著書に『江戸三〇〇藩城下町をゆく』(双葉社)、『戦術の日本史』(宝島社)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。