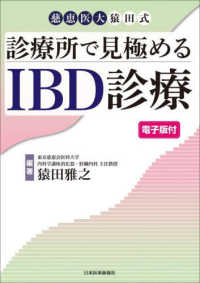- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
いかにしておいしく食べ、よりよく生きるのか―。地球の持続可能性の問題を背景に、アーレント、メルロ=ポンティ、ハンス・ヨナス、レヴィナスをはじめとする西洋哲学における人間中心主義を、日常の“食べる”ことから問い直す。アクターネットワーク理論の果ての、この世界を生き抜くための知のレシピ。
目次
第1章 経験哲学
第2章 ある
第3章 知る
第4章 する
第5章 関わる
第6章 知の食材
著者等紹介
モル,アネマリー[モル,アネマリー] [Mol,Annemarie]
1958年、オランダ、シャースベルフに生まれる。アムステルダム大学教授。人類学者、哲学者
田口陽子[タグチヨウコ]
1980年、広島県に生まれる。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(社会学)。現在、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部准教授。専門は文化人類学、南アジア地域研究
浜田明範[ハマダアキノリ]
1981年、東京都に生まれる。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(社会学)。現在、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻准教授。専門は医療人類学、アフリカ地域研究
碇陽子[イカリヨウコ]
1977年、福岡県に生まれる。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。現在、明治大学政治経済学部専任講師。専門は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
文狸
1
なぜ「食べる」に注目するのか。「政治的存在」をもって人間を自然から切断しようとしたアーレントと対置された導入によって、その意義がまずわかるようになっている。それぞれの章立ては大胆と言っていいほど哲学の大きなテーマ(「ある」「する」「関わる」……)を掲げていて、文章からも古典的文献をもとに論じる姿勢が窺われる(かつ、高い可読性を保ち続ける彼女の筆致は素晴らしい)。「ある」は嚥下のフィールドノートから始まり、内と外の境界を考えるうえで「食べる」がキーになってくることを読者に明示する。2024/06/17
KATSUOBUSHIMUSHI
1
食べる状況を参照しながら階層的な思考が残る哲学用語を変容させ、環境破壊に対応できるオルタナティブな理論的ツールを描く本。「自由民」の会話に相当するものとしてケアに注目することで、持続可能で人間以外を含む政治がすでに行われてきたことを明らかにする。フィールドノートは食に関するあるあるや子供も思いつきそうな素朴な考えも多く含むなじみ深いものだが、そんな状況を既存の枠組みから逃れるための武器に使っているので、読んでいると当たり前じゃん!という感想とラディカルすぎる!という感想を同時に抱いて不思議な気分になった。2024/05/19
-

- 和書
- 刺客 文春文庫