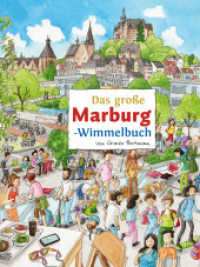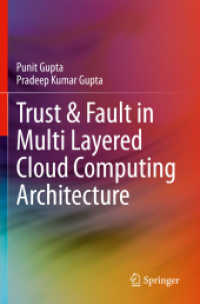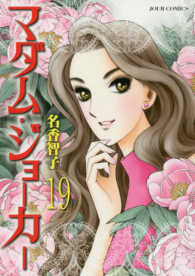内容説明
若き日のボードレール体験や「マチネ・ポエティク」の活動を通じて得た詩の富を小説においても展開すべく、作中で様々な実験を重ね、散文詩や音楽に限りなく近い独自の文学世界を構築した福永武彦。代表作である『風土』や『海市』、「塔」「冥府」「廃市」などの短篇、そして作家最大の到達点『死の島』を読み解き、そこに結晶化した詩学の相貌を探る。
目次
第1章 フランス文学者福永武彦の冒険―「マチネ・ポエティク」から『死の島』へ
第2章 詩と音楽―ボードレールから福永武彦へ(1)
第3章 憂愁の詩学―ボードレールから福永武彦へ(2)
第4章 冥府の中の福永武彦―ボードレール体験からのエスキス
第5章 冥府からの展開―「廃市」『海市』そして『死の島』へ
第6章 死のポリフォニー―引用で読む『死の島』論
第7章 ポエティクvsロマネスク―中村真一郎と福永武彦
書評三篇
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月
4
福永武彦にとって詩は、まず郷愁の行為としてはじまったと、以前菅野昭正氏が触れていた。そして詩の読者は小説を読むように(或いはその逆も)招待されていると・・。福永の詩や小説の根底に眠るものはボードレール(詩学)であることは周知の事実ではあるが、本書著者の語る、風土、塔、冥府、深淵、廃市、海市、死の島への誘い(論考)は、今回改めて別視点にて考えさせられ興味深かった。まだまだ未読の福永小説やボードレール関連の積読本が本棚に眠っているので、著者が巻末で取り上げている他者論考を含め、時間を掛けて読み解いてゆきたい。2019/12/30
里十井円
0
「だが、あらゆる芸術の中でとりわけ音楽が重視されるのは、その徹底した暗示性の故である。それは、一つの音楽乃至旋律がある影像を喚起する、という意味での暗示性ではない。音楽とは全ての影像を許容しつつ無価値化する純粋観念に他ならない。音楽は常に「空間の観念」を与えるのみで、凝固した物質として(美術のように)、あるいは固定された記号として(言語のように)、空間に痕跡を留めることは、決してない。それは魂に霊的な場を与えながら自らは存在しない、つまり意味作用を持ちながら意味を持たない暗示能力として、詩的宇宙の極北に2024/01/24
-

- 和書
- カラー武蔵野の魅力