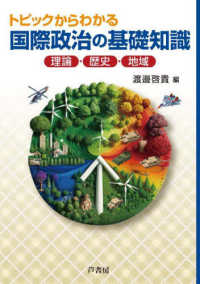出版社内容情報
近年の初期室町幕府研究は、若手研究者の台頭により豊富な研究蓄積がある。十四世紀の南北朝時代そのものを扱った通史はたくさん存在するが、初期室町幕府を基軸に据えて、同政権が対南朝で苦戦や試行錯誤を重ねながらも、政権基盤を確立し、発展していく様相を叙述した書籍はほとんどない。本書は、成立から最盛期(義満期)に至るまでの初期室町幕府について、政治体制・地方統治・室町殿義満・寺院政策など、最先端の研究動向を紹介。なお、初期室町期とは、幕府成立から南朝と平行し、義満の時代に幕府が最盛期を迎える時期を指す。
内容説明
「初期室町幕府」は、どの時代を指すのか?十五代続いた幕府の中で、「初期」とは足利尊氏、義詮、義満三代のあたりを指すらしい。実はこの頃が、幕府のもっとも輝いていた時代だった。「歴史の常識」に気鋭の研究者たちが大太刀を振るう。
目次
はじめに―なぜ今、草創期の室町幕府なのか?
第1部 初期室町幕府の政治体制(軽視されてきた軍事史研究―初期室町幕府には、確固たる軍事制度があったか?;主従制的支配権と統治権的支配権―足利尊氏・直義の「二頭政治論」を再検討する ほか)
第2部 有力守護および地方統治機関(初期室町幕府と幕政改革―脚光を浴びつつある「観応の擾乱」以降の幕府政治;三管領の研究史―研究対象は、細川・畠山・斯波氏だけでいいのか? ほか)
第3部 室町殿・足利義満の位置づけ(室町殿の研究史―過大に評価されがちな「義満権力」を再検討する;義満と東アジアの国際情勢―「日本国王」号と倭寇をめぐる明皇帝の思惑とは? ほか)
第4部 初期室町幕府の寺院・宗教政策(初期室町幕府と禅律方―禅院・律院を体制仏教の中心とした幕府の宗教政策;室町将軍家の菩提寺―室町仏教を代表する官寺、相国寺創建の意義とは? ほか)
著者等紹介
亀田俊和[カメダトシタカ]
1973年秋田生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。京都大学博士(文学)。国立台湾大学日本語文学系助理教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
サケ太
組織液
nagoyan
六点